「地球環境を大切にしましょう」「自然を守りましょう」という言葉を、私たちは日常的に耳にします。でも、なぜそれがそんなに重要なのでしょうか?
毎朝起きて顔を洗うときの透明できれいな水、深呼吸したときに肺いっぱいに入ってくる新鮮な空気、栄養たっぷりでおいしい野菜や果物。これらすべては、地球という壮大な自然システムが私たちに与えてくれる、かけがえのない恵みなのです。
ところが現在、この美しい地球の自然環境が、さまざまな理由で少しずつ変化し、危機的な状況に向かっていると専門家たちは指摘しています。気候変動、海洋汚染、森林の減少など、大きな問題がたくさんあります。
でも、心配ばかりしていても始まりません。私たち一人ひとりができること、特に子どもたちと一緒に楽しく取り組めることがたくさんあるのです。難しく考える必要はまったくありません。普段の生活の中で、ちょっとした意識を変えるだけで、地球に優しい暮らしは始められます。
この記事では、親子で楽しみながら実践できる環境に優しい行動を7つ厳選してご紹介します。どれも今日から始められるものばかりですので、ぜひ参考にしてみてください。
環境を守るってどういうこと?子どもに伝えたい3つの基本的な考え方
具体的な行動をお話しする前に、まずは「環境を大切にする」という気持ちの土台となる、3つの基本的な考え方をお子さんと共有してみましょう。これらの考え方を理解することで、なぜ環境を守る必要があるのかが、子どもたちにもわかりやすく伝わります。
1. 自然からの贈り物に心から感謝する
私たちの食卓を彩るカラフルな野菜、プリプリのお魚、ジューシーなお肉。これらの食材は、すべて地球という大きな自然からいただいた大切な「命」です。毎日の「いただきます」と「ごちそうさま」は、単なる挨拶ではありません。「このトマトを育ててくれた畑の土さん、ありがとう」「太陽の光をたくさん浴びて甘くなったりんご、ありがとう」「大海原で元気に泳いでいたお魚さん、命をありがとう」という、深い感謝の気持ちを表現する言葉なのです。
子どもたちには、食べ物がどこから来て、どんな風に育てられたのかを想像してもらいましょう。そうすることで、自然への感謝の心が自然と育まれていきます。
2. 地球の資源を無駄遣いしない工夫をする
お子さんの大切なおもちゃ、毎日着ている洋服、学校で使う文房具。これらはすべて、地球の限りある資源である木材、石油、金属などから作られています。「もう飽きたから捨てよう」「新しいのを買ってもらおう」と簡単に考えてしまうと、その分だけ貴重な資源が消費され、同時にたくさんのゴミが生まれてしまいます。
「まだ使えるおもちゃは、他の遊び方を考えてみよう」「服に小さな穴が開いても、お母さんと一緒に可愛く補修してみよう」「使い終わった紙の裏側にお絵描きしてみよう」など、ものを大切に長く使う工夫をすることは、地球の資源を守ることに直結しています。
3. すべての生き物の命を大切に思う
お散歩中に見つけた道端の小さな花、公園の砂場で一生懸命働いているアリの行列、葉っぱの陰でまんまるになっているダンゴムシ。どんなに小さな生き物にも、私たち人間と同じように、かけがえのない命が宿っています。
「綺麗な花だから摘んで持って帰ろう」ではなく、「ここで咲いているから、通りかかった人みんなが嬉しい気持ちになれるね」と考える。「アリを踏んづけちゃえ」ではなく、「アリさんも大切な家族のところに帰るんだね。道を開けてあげよう」と思いやる。そんな優しい心が、自然環境を守る大きな力になるのです。
今日から始められる!おうちでできる環境に優しい取り組み5選
基本的な考え方を確認したところで、いよいよ具体的なアクションを見ていきましょう。まずは、お家の中で気軽に始められる環境に優しい活動をご紹介します。どれも特別な道具や準備は必要ありませんので、親子で楽しく挑戦してみてください。
1. 電気と水を大切に使って地球のエネルギーを守ろう
毎日当たり前に使っている電気と水道水。でも、これらを作り出すためには、実はたくさんの自然の力や資源が必要になることを、お子さんと一緒に考えてみましょう。
「誰もいないお部屋の電気は消そうね」「見ていないテレビはOFFにしようね」「歯磨きの時は、必要な分だけ水を出そうね」「お風呂のお湯は家族みんなで順番に使おうね」といった、日常の小さな習慣を大切にすることから始めてみてください。
子どもたちには、「電気を作るためには川の水を使ったり、石炭を燃やしたりするんだよ」「水道水を綺麗にするためには、たくさんの機械が働いているんだよ」ということを、年齢に応じてわかりやすく説明してあげると良いでしょう。節電・節水が地球を守ることにつながっているという実感を持ってもらえます。
2. ゴミの分別マスターになって資源の再活用を応援しよう
毎日出るゴミも、実は立派な「資源」に生まれ変わる可能性を秘めています。ペットボトル、アルミ缶、牛乳パック、段ボール、古新聞など、正しく分別することで、これらは新しい製品の材料として再利用されるのです。
「このペットボトルは、何に変身すると思う?」「牛乳パックから、新しいティッシュペーパーができるんだって!すごいね!」といったクイズ形式で楽しく分別作業を進めると、子どもたちも積極的に参加してくれるでしょう。
また、資源回収の日に一緒に出しに行って、「たくさんの人が協力すると、こんなにたくさんの資源が集まるんだね」ということを実際に見せてあげるのも効果的です。リサイクルの大切さと面白さを、体験を通して学んでもらいましょう。
3. 食材を無駄なく使い切ってフードロス問題に取り組もう
現在、世界中で深刻な問題となっているのが、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品の無駄遣い(フードロス)です。日本でも、年間で非常に多くの食品が廃棄されており、これは環境に大きな負担をかけています。
ご家庭では、「野菜の皮や茎も、工夫次第で美味しい料理になるよ」「大根の葉っぱは、炒め物にするととっても美味しいんだって」「りんごの皮も、よく洗えば栄養がたっぷり!」など、食材を最後まで活用する方法を親子で探してみましょう。
また、冷蔵庫の中身を定期的にチェックして、「このお野菜、早めに使わないと傷んじゃうね。今日のお料理に使おうか」と計画的に消費することも大切です。食べ物への感謝の気持ちを示すと同時に、ゴミを減らす立派な環境活動になります。
4. 家庭用コンポストで生ごみを宝物に変えてみよう
少しレベルアップした取り組みとして、家庭用のコンポスト(生ごみ処理器)を使って、野菜の切りくずや果物の皮などから、植物にとって栄養満点の堆肥を作る方法があります。これは、自然界の循環システムを家庭で体験できる、とても貴重な学習機会です。
「昨日捨てた野菜のくずが、今日はもうこんなに変化してる!」「なんだか土の良い匂いがしてきたね」「この堆肥で育てた野菜は、きっと元気いっぱいに育つね」など、生ごみが土の栄養に変わっていく過程を親子で観察するのは、まるで科学実験のようで楽しいものです。
完成した堆肥を使って、ベランダや庭で小さな家庭菜園に挑戦してみるのもおすすめです。自分たちで作った堆肥で育てた野菜を収穫して食べるという体験は、食べ物と環境のつながりを実感できる貴重な機会になるでしょう。
5. 環境に関する本や映像で知識と関心を深めよう
図書館や書店には、動物や海の生き物、森や川の自然、地球環境について学べる本がたくさんあります。美しい写真がたくさん載った図鑑や、子ども向けにわかりやすく書かれた環境問題の本を一緒に読んでみましょう。
また、テレビやインターネットで視聴できる自然ドキュメンタリー番組もおすすめです。「すごい!こんな動物がいるんだね」「この森がなくなったら、動物たちはどこに住むんだろう」「海がきれいだと、お魚たちも元気なんだね」など、映像を見ながら親子で感想を話し合うことで、自然への興味と守りたいという気持ちが自然と育まれます。
普段は見ることのできない世界の自然や、そこに住む生き物たちの生活を知ることで、地球の素晴らしさと、それを守ることの大切さを実感してもらいましょう。
外に出て体感しよう!自然とふれあう活動2選
お家での取り組みに慣れてきたら、今度は実際に外に出て、五感を使って自然を感じられる活動に挑戦してみましょう。自然の中で過ごす時間は、子どもたちの環境への意識を高める最も効果的な方法の一つです。
1. 地域の清掃活動で街と自然をきれいにしよう
普段のお散歩や公園遊びの際に、落ちているゴミを見つけたら一つ拾ってみる。それだけでも、地域の環境をきれいにする素晴らしい一歩になります。「このゴミがここにあると、お花が悲しんでいるかもしれないね」「きれいな公園だと、みんなが気持ちよく過ごせるね」と話しながら行うことで、環境への配慮の心を育てることができます。
もし地域で清掃活動やボランティア活動が開催されていれば、親子で参加してみるのも良い経験になります。「たくさんの人が協力すると、こんなにきれいになるんだね」「みんなで力を合わせると、大きなことができるんだね」という達成感を味わいながら、社会貢献への意識も芽生えさせることができるでしょう。
清掃活動の後は、「動物たちも喜んでいるかな」「次に来る人たちが気持ちよく過ごせるね」と、自分たちの行動がどんな良い影響を与えるかを一緒に考えてみてください。
2. 身近な自然を観察して小さな発見を楽しもう
特別な場所に出かけなくても、近所の公園、街路樹、道端の花壇には、たくさんの自然の宝物が隠れています。「この鳥さんはどんな名前かな?どこから飛んできたのかな?」「昨日より花の数が増えてるね」「このちょうちょは何色が好きなのかな?」など、親子で自然探偵になってみましょう。
スマートフォンのアプリを使って、見つけた植物や昆虫の名前を調べてみるのも、現代ならではの楽しい自然観察の方法です。「この花の名前がわかったよ!」「この虫はこんな特徴があるんだって!」という発見は、子どもたちの好奇心をさらに刺激してくれます。
季節ごとの変化を観察するのもおすすめです。春には新緑や花の開花、夏には昆虫の活動、秋には紅葉や木の実、冬には霜や氷の結晶など、一年を通じて自然の美しさと不思議さを体験することで、自然への愛着がより深まっていきます。
継続するためのコツ:年齢に応じた取り組み方
環境に優しい取り組みを長続きさせるためには、お子さんの年齢や興味に合わせてアプローチを工夫することが大切です。
幼児期(3~6歳)
この時期の子どもたちには、楽しく遊びながら学べる要素を取り入れることが重要です。「電気を消すときは忍者みたいにそーっとね」「ゴミ分別ゲーム、今日は何点かな?」など、ゲーム感覚で取り組めるように工夫してみましょう。また、絵本や歌を使って環境について学ぶのも効果的です。
小学生(7~12歳)
理解力が高まるこの時期には、「なぜそうするのか」という理由も含めて説明してあげましょう。「電気を作るにはこんな方法があって…」「リサイクルするとこんな良いことがあって…」など、少し詳しい情報も交えながら、知的好奇心を満たしてあげることが大切です。
まとめ:小さな一歩が大きな変化を生み出す
環境を大切にする取り組みは、決して特別で難しいことではありません。今回ご紹介した7つの活動は、どれも私たちの日常生活の延長線上にある、身近で実践しやすいものばかりです。
大切なのは、完璧を目指すことではありません。「今日はこれをやってみよう」「今週はこの活動に挑戦してみよう」といった具合に、親子で「これなら楽しくできそう!」と思える取り組みを一つずつ見つけて、気楽に始めてみることです。
子どもたちが自然を思いやる優しい心を育むこと、そして環境を大切にする習慣を身につけること。これらは、子どもたちの明るい未来と、美しい地球環境の保全に向けた、最も価値ある贈り物となるでしょう。
今日という日から、親子で一緒に、地球に優しい暮らしの第一歩を踏み出してみませんか?きっと、思っていた以上に楽しく、やりがいのある取り組みになるはずです。
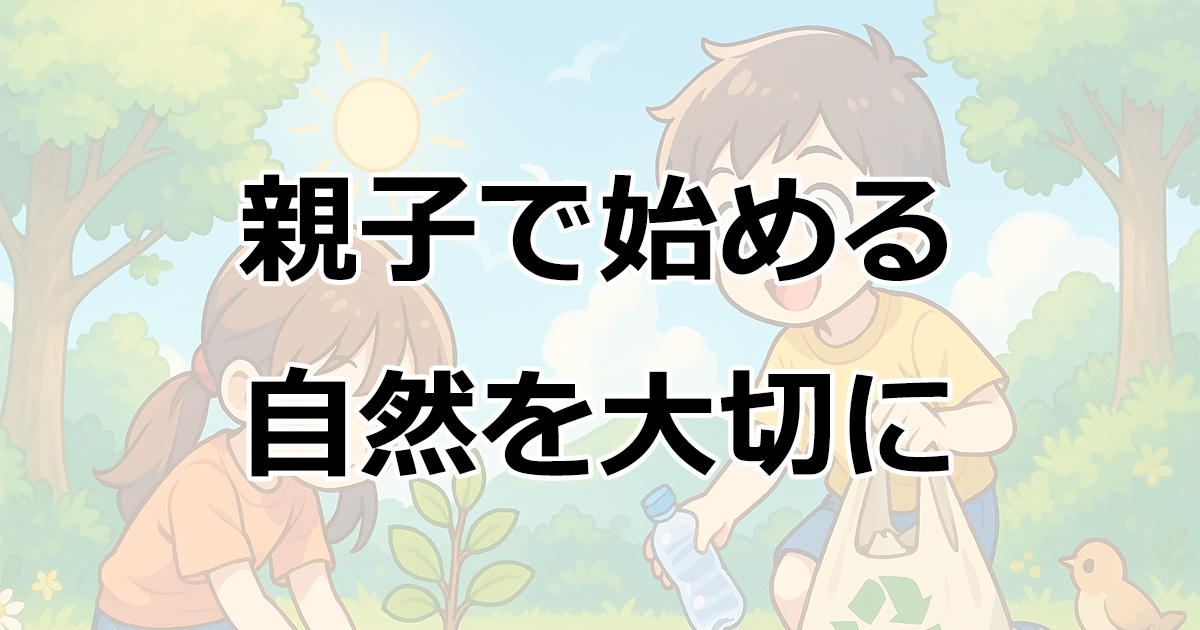
コメント