「今年の十五夜は、新暦だといつ?」 「結婚式は大安がいいけど、旧暦とも関係があるのかな?」
私たちの生活に深く根付いているようで、実はよく知らない「旧暦」。 カレンダーでおなじみの「新暦」とは、日付が1ヶ月ほどズレていることもあり、少し複雑に感じるかもしれません。
この記事では、そんな旧暦の「?」にすぐお答えできるよう、2025年の新暦と旧暦の対応が一覧でわかる早見表をご用意しました。
さらに、単なる日付の確認だけでなく、
- 新暦と旧暦、なぜズレるの?
- 六曜(大安・仏滅など)や二十四節気の仕組み
- 旧暦を知ると見えてくる、日本の伝統行事の本当の意味
など、あなたの毎日を少し豊かにする旧暦の知識を、わかりやすく解説していきます。この記事を読めば、旧暦がもっと身近な存在になるはずです。
2025年 旧暦・新暦対応 早見表
まずは、2025年の日付を確認してみましょう。 主要な祝日、伝統行事、そして季節の節目となる「二十四節気」を記載しています。
上半期(1月~6月)
| 新暦(2025年) | 旧暦 | 六曜 | 主な行事・二十四節気 |
|---|---|---|---|
| 1月20日 | 12月21日 | 友引 | 大寒 |
| 1月29日 | 1月1日 | 先勝 | 旧正月(春節) |
| 2月4日 | 1月7日 | 友引 | 立春 |
| 2月12日 | 1月15日 | 先負 | 旧暦の小正月 |
| 2月19日 | 2月2日 | 先負 | 雨水 |
| 3月5日 | 2月16日 | 先勝 | 啓蟄 |
| 3月20日 | 3月2日 | 先勝 | 春分 |
| 4月5日 | 3月18日 | 仏滅 | 清明 |
| 4月20日 | 4月23日 | 赤口 | 穀雨 |
| 5月5日 | 4月8日 | 先負 | 立夏・端午の節句 |
| 5月21日 | 5月5日 | 先勝 | 小満 |
| 6月6日 | 5月21日 | 赤口 | 芒種 |
| 6月21日 | 6月6日 | 先勝 | 夏至 |
下半期(7月~12月)
| 新暦(2025年) | 旧暦 | 六曜 | 主な行事・二十四節気 |
|---|---|---|---|
| 7月7日 | 6月12日 | 仏滅 | 小暑・七夕 |
| 7月23日 | 7月28日 | 仏滅 | 大暑 |
| 8月3日 | 7月9日 | 大安 | 旧暦の七夕 |
| 8月8日 | 7月14日 | 先負 | 立秋 |
| 8月23日 | 8月1日 | 先負 | 処暑 |
| 9月8日 | 8月17日 | 友引 | 白露 |
| 9月23日 | 9月2日 | 友引 | 秋分 |
| 10月6日 | 9月15日 | 先勝 | 中秋の名月(十五夜) |
| 10月8日 | 9月17日 | 友引 | 寒露 |
| 10月23日 | 10月3日 | 友引 | 霜降 |
| 11月3日 | 10月13日 | 先負 | 十三夜 |
| 11月7日 | 10月17日 | 友引 | 立冬 |
| 11月22日 | 11月2日 | 友引 | 小雪 |
| 12月7日 | 11月17日 | 赤口 | 大雪 |
| 12月22日 | 12月2日 | 赤口 | 冬至 |
そもそも旧暦とは?新暦との違い
なぜ「旧暦」と「新暦」では日付が違うのでしょうか。それぞれの暦が拠り所にしているものが、根本的に異なるからです。
旧暦(太陰太陽暦)の基本
旧暦は、月の満ち欠けの周期を基準にした暦です。「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」とも呼ばれます。
- 新月(月が見えない日)を毎月の1日(ついたち)とする
- 月が満ち欠けする周期は約29.5日なので、1ヶ月は29日(小の月)か30日(大の月)になる
- 12ヶ月で約354日となり、新暦より11日ほど短くなる
かつて農業や漁業が中心だった時代、月の満ち欠けは潮の満ち引きにも影響するため、生活に欠かせない指標でした。
現在使われている新暦(グレゴリオ暦)
一方、私たちが普段使っている新暦は、地球が太陽の周りを一周する期間を基準にした暦です。「グレゴリオ暦」や「太陽暦」とも呼ばれます。
- 地球が太陽を一周する期間は約365.24日
- これを12ヶ月に分け、1年を365日とする
- ズレを調整するために、4年に1度「うるう年」を設けて366日にする
季節の移り変わりは太陽の動きと連動するため、太陽暦である新暦は、実際の季節と日付が大きくズレることがありません。
なぜ約1ヶ月のズレが生まれるのか?
旧暦の1年(約354日)と新暦の1年(約365日)では、約11日間の差があります。 この差が積み重なり、3年経つ頃には約1ヶ月ものズレが生じます。そのため、旧暦と新暦の日付は毎年変動し、おおよそ1ヶ月前後ズレることになるのです。
旧暦の仕組みをわかりやすく解説
月の満ち欠けを基準にすると、季節がどんどんズレていってしまいます。この問題を解決するため、旧暦には素晴らしい知恵が詰まっています。
日付の基準は「月の満ち欠け」
旧暦の日付は、月の形で直感的にわかります。
- 1日(朔・ついたち): 新月
- 15日頃(望・もちづき): 満月
- 30日頃(晦・つごもり): 月が隠れる日
「十五夜お月さん」という言葉があるように、旧暦15日は必ず満月の頃にあたります。
季節のズレを補う「閏月(うるうづき)」
月の満ち欠けだけを基準にすると、1年で約11日ずつ季節がズレていきます。数年経つと、4月なのに真冬、という事態になりかねません。
そこで、このズレをリセットするために挿入されるのが**「閏月(うるうづき)」**です。 およそ3年に1度(正確には19年に7回)、1年を13ヶ月にして季節のズレを調整します。これにより、暦と実際の季節が大きく乖離するのを防いでいるのです。
季節の指標となる「二十四節気(にじゅうしせっき)」
月のリズムを使いながらも、季節感を正確に把握するために取り入れられたのが「二十四節気」です。
これは太陽の動きに基づいています。1年を24等分し、それぞれに「立春」「夏至」「秋分」「冬至」といった季節を表す名前を付けました。
旧暦を知るともっと面白い!日本の暦と文化
旧暦の考え方は、今も日本の文化に深く息づいています。
日にちに「意味」を与える六曜(ろくよう)
カレンダーでよく見かける「大安」や「仏滅」は「六曜」と呼ばれるものです。 これは旧暦そのものではなく、日の吉凶を占う一種の指標ですが、旧暦カレンダーに併記されることが多いため、関連が深いものとして定着しています。
- 先勝(せんしょう): 午前は吉、午後は凶
- 友引(ともびき): 慶事には良いが、葬儀は避ける
- 先負(せんぶ): 午前は凶、午後は吉
- 仏滅(ぶつめつ): 一日を通して凶
- 大安(たいあん): 一日を通して大吉
- 赤口(しゃっこう): 正午のみ吉、それ以外は凶
旧暦で読み解く伝統行事の本当の意味
なぜその行事がその日に行われるのか、旧暦で考えると理由が見えてきます。
- 七夕: 新暦の7月7日は梅雨の真っ只中ですが、旧暦の7月7日(8月上旬頃)は梅雨が明け、天の川が美しく見える時期です。
- 中秋の名月: 旧暦8月15日の夜に見える月のこと。秋は空が澄み渡り、月が最も美しく見える季節とされていました。
- お盆: 旧暦7月15日を中心に行われていた先祖供養の儀式です。現在、東京などでは新暦の7月15日、その他の多くの地域では新暦の暦を使いつつ1ヶ月遅らせた「月遅れ盆」である8月15日に行われます。
旧暦のリズムを取り入れる、現代の暮らしのヒント
旧暦は過去のものではありません。そのリズムは、私たちの心と体に優しく寄り添ってくれます。忙しい毎日の中に、少しだけ季節の感覚を取り入れてみませんか。
月の満ち欠けを意識して過ごす
月のリズムは、私たちの心身のサイクルにも影響を与えると言われています。
- 新月(始まり): 新しいことを始める、目標を立てるきっかけに。
- 満月(達成): これまでの頑張りを振り返り、リラックスして過ごす目安に。
二十四節気を旬の食材で味わう
二十四節気は、まさに自然界の旬を知らせるカレンダーです。
- 穀雨(4/20頃): 瑞々しい春キャベツやタケノコを食卓に。
- 大暑(7/23頃): 体を冷やすキュウリやトマトなどの夏野菜をたっぷり。
- 霜降(10/23頃): 滋味深いキノコや根菜を使った料理を楽しむ。
季節の変わり目を「しつらえ」で楽しむ
季節の節目に、暮らしに小さな変化を加えてみましょう。
- 立春(2/4頃): 梅の枝や菜の花を飾ってみる。
- 処暑(8/23頃): 朝夕の涼しい風を感じながら、風鈴の音に耳をすませる。
- 冬至(12/22頃): ゆず湯に入って、心と体を温める。
旧暦に関するQ&A
- 今年の旧正月はいつ?
-
2025年の旧正月(旧暦1月1日)は、新暦の1月29日です。
- 十三夜って何?
-
旧暦9月13日の夜のことです。中秋の名月(十五夜)に次いで美しい月とされ、十五夜の月見をしたら、必ず十三夜の月見もするものとされていました。2025年の十三夜は、新暦の11月3日です。
- 旧暦の1年は何日?
-
通常の年は12ヶ月で約354日、閏月が入る年は13ヶ月で約384日になります。
まとめ
この記事では、2025年の旧暦・新暦対応表から、旧暦の仕組み、そして現代の暮らしに活かすヒントまでを解説しました。
- 旧暦は「月の満ち欠け」を基準にした暦
- 新暦は「太陽の動き」を基準にした暦
- 旧暦は「閏月」や「二十四節気」で季節のズレを調整している
- 伝統行事や六曜など、旧暦は今の日本の文化にも深く根付いている
旧暦を知ることは、私たちが忘れかけていた日本の豊かな四季や、自然と共にあった昔の人々の暮らしに思いを馳せるきっかけになります。
ぜひこの記事の早見表をご活用いただき、日々の生活の中で季節の移ろいを感じてみてください。
#この記事の作成にあたり参考にした情報
この記事は、読者の皆様に正確な情報をお届けするため、以下の公的機関や専門機関の情報を参考に作成しています。
- 国立天文台 暦計算室
- こよみのページ
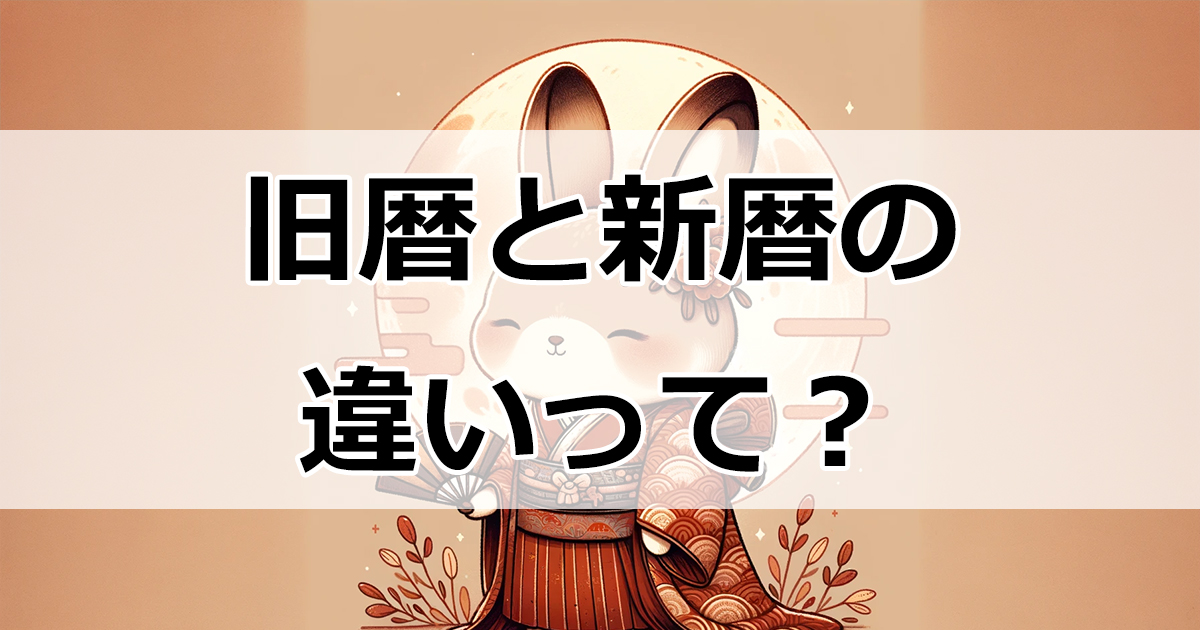
コメント