「なんだかとても楽しそうにしているけれど、何があったのか聞いても教えてくれない」
「明らかに嫌なことがあったみたいなのに、どうしたのかと尋ねても黙り込んでしまう」
お子さんのこんな様子を見かけて、「本当はどんな気持ちなのだろう?」「どうして自分の気持ちを話してくれないのだろう?」と、歯がゆい思いをされたことはありませんか。
言葉にならない子供の心の中を想像しながら、どのように接したらよいのか戸惑ってしまったり、「もしかすると、私の子育ての仕方に問題があるのでは…」と心配になったりすることもあるかもしれません。
でも、そんなお悩みを抱えているのは、決してあなただけではありません。実際のところ、多くのお子さんが、自分の内側にある気持ちを適切な言葉で表現することに困難を感じています。
この記事では、どうして子供が感情を言葉で表現するのが得意でないのか、その背景にある理由を分かりやすく説明していきます。そして、発達心理学の研究成果や子育て支援の現場で重視されている考え方をもとに、ご家庭で今すぐに始められる「親子の心が深く通い合う6つのコミュニケーション方法」を、実際の会話例とともに詳しくご紹介します。
この記事を最後まで読んでいただくことで、お子さんの心の奥底にある気持ちを理解し、その感情に温かく寄り添うための、実践的で具体的な方法を見つけていただけることでしょう。
子供が気持ちを言葉で表現するのが難しい5つの背景
子供が感情をスムーズに表現できないのには、子供なりの理由と背景があります。まずは、その根本的な要因を理解することから始めていきましょう。
1. 気持ちを表現する「語彙」がまだ身についていない
私たち大人は「嬉しい」「悲しい」「悔しい」「不安」といった感情を表す言葉を自然に使い分けることができますが、子供が自分の感情を表現するためには、まずその気持ちに対応する適切な言葉を知っている必要があります。
特に小さなお子さんの場合、まだ感情を表現するための語彙が十分に蓄積されていないため、心の中でぐるぐると渦巻いているモヤモヤした気持ちを、ぴったりと当てはまる言葉で表現することが非常に困難なのです。
発達段階別の感情語彙の特徴
• 2〜3歳:「いやだ」「うれしい」などの基本的な感情語
• 4〜5歳:「びっくりした」「さみしい」など、やや複雑な感情語
• 6〜8歳:「がっかりした」「ほっとした」など、状況に応じた感情語
2. 自分が今感じている感情が「何」なのかを識別できない
たとえ感情を表す言葉を知っていたとしても、今この瞬間に自分が感じているこの気持ちが「怒り」なのか「悲しみ」なのか、あるいは「不安」なのかを、自分自身で正確に区別することができない場合もよくあります。
これは、心の感情と身体の感覚が十分に結びついていないためです。どうして涙がこぼれてくるのか、どうして胸がドキドキするのか、どうして手に汗をかくのかといった身体的な反応と、それに対応する感情の名前を、自分の中で整理できていない状態なのです。
3. 感情を安心して表現できる心理的環境が整っていない
もしもお子さんが過去に感情を素直に表現したときに、「泣くのはやめなさい!」「そんなわがままを言ってはダメ」といった形で否定的な反応を受けた経験があると、「この気持ちは出してはいけないものなんだ」と無意識のうちに心を閉ざすようになってしまいます。
また、家庭内にいつも緊張感が漂っていたり、保護者の方がとても忙しそうにしていたりする状況では、子供は「迷惑をかけてはいけない」「心配をかけてはいけない」という気持ちから、自分の本当の感情を奥深くに押し込めてしまうことがあります。
4. 身近な大人が感情表現のモデルを示していない
子供は身近な大人、特に保護者の姿を見て、多くのことを自然に学んでいきます。もし保護者の方が日常的に「今日はとても嬉しいな!」「さっきのこと、実はすごく悲しかったんだよ」といったように感情を素直に言葉にしていると、子供も「こんなふうに気持ちを伝えても大丈夫なんだ」ということを学習していきます。
反対に、保護者の方があまり感情を表に出さないタイプの場合、子供はどのように自分の気持ちを表現すればよいのか、具体的な方法が分からなくなってしまいます。
5. 生まれ持った気質や現在の発達段階による影響
生まれつき内向的で、自分の気持ちをじっくりと内側で整理してから表現するタイプのお子さんもいらっしゃいます。このようなお子さんの場合、感情を言葉にするまでに、ある程度の時間が必要なのです。
また、特に小学校に入学する頃になると、お友達との関係を意識するようになり、「これを言ったら相手にどう思われるだろうか」「みんなと違うことを言っても大丈夫だろうか」といったことを考えるようになり、自分の本音を率直に表現することが難しくなることもあります。これは、社会性が発達している証拠でもあります。
この章で大切にしたいポイント
子供が感情をうまく表現できないのは、言葉の発達、環境的な要因、そして成長の過程など、さまざまな要素が複雑に絡み合っているからです。決して、お子さん自身の能力や、保護者の方の育て方だけに原因があるわけではありません。
発達段階に応じた!子供の感情表現を豊かに育む6つのアプローチ方法
お子さんの心の中にある気持ちに優しく寄り添い、その表現をサポートするために、保護者の方ができることは実はたくさんあります。ここでは、具体的な6つのアプローチ方法を、実際の会話例やシーン例とともに詳しくご紹介します。お子さんの年齢や個性に合わせて、取り組みやすいものから少しずつ試してみてください。
1. 子供が感じている感情に「適切な名前」を付けてサポートする
お子さんが感じているであろう気持ちを、大人が適切な言葉にして教えてあげることを、心理学では「感情のラベリング」と呼びます。これは、自分の気持ちを理解し、表現するための重要な第一歩となります。
良い関わり方の具体例
「お友達におもちゃを快く貸してあげられたね。きっと、とても誇らしい気持ちになったんじゃないかな」
「かけっこで転んでしまったんだね。痛かったし、思うようにいかなくて悔しい気持ちだったね」
「公園から帰る時間になったけど、まだまだ遊んでいたかったから、残念な気持ちなんだね」
年齢別のアプローチのコツ
• 2〜4歳頃:「うれしい」「かなしい」「いやだ」など、シンプルで理解しやすい言葉から始めましょう
• 5〜7歳頃:「びっくりした」「がっかりした」「ほっとした」など、少し複雑な感情の言葉も使っていくと、表現の幅が広がります
• 8歳以上:「もどかしい」「複雑な気持ち」「誇らしい」など、より微細な感情表現も取り入れてみましょう
2. どのような気持ちであっても「まずは受け止める」姿勢を大切にする
たとえネガティブな感情や、大人から見ると理不尽に思える気持ちであっても、「そんなふうに感じたんだね」と、まずは否定や評価をせずにそのまま受け止めてあげることが重要です。「あなたの気持ちは間違っていないよ」「あなたの感情は大切なものだよ」というメッセージが、お子さんの心の安全感につながります。
受け止める関わり方の例
子:「弟ばっかりズルい!いつも弟の方ばかり可愛がっている!」
親:「そうか、弟くんばかりがえこひいきされているって感じたんだね。どんなところを見て、そんなふうに思ったのか、よかったら教えてくれるかな?」
避けたい対応の例
子:「弟ばっかりズルい!いつも弟の方ばかり可愛がっている!」
親:「そんなことないでしょ!お兄ちゃんなんだから我慢しなさい!」
良い・悪いといった判断をすぐに下すのではなく、まずはお子さんの気持ちに共感する姿勢を示すことが、信頼関係を築く上で非常に大切です。
3. 保護者自身が「感情表現の良いお手本」となる
保護者の方自身が、日常生活の中で自分の感情を自然に言葉にしている姿を見せることで、お子さんにとって最高の「感情表現のモデル」となります。完璧である必要は全くありません。保護者の方も一人の人間として、さまざまな気持ちを感じることを、ありのままに表現してあげてください。
日常での感情表現の例
「わあ、今日の夕焼けはとてもきれいだね。お母さん、なんだかとても穏やかで幸せな気持ちになるよ」
「探していたものがなかなか見つからないなあ。うーん、少し困ったような、焦ったような気持ちだよ」
「あなたが自分から手伝ってくれて、お父さんは本当に嬉しいよ!心から感謝している気持ちだよ」
4. 日常的に「気持ちを分かち合う時間」を意識的に作る
意識的に、お互いの気持ちについて話し合う時間を設けることで、お子さんも感情を言葉にすることに慣れていきます。特別な時間を作る必要はなく、日常の中の自然なタイミングを活用してみましょう。
気持ちシェアタイムの具体例
夕食の時間に:「今日一日で、一番『嬉しかったこと』は何だったかな?」
お風呂での時間に:「今日、一番『楽しかったこと』と、一番『困ったこと』があったら教えて!」
寝る前の静かな時間に:一日の出来事を振り返りながら、ゆっくりと気持ちを話し合う時間にする
保護者の方がまず自分の気持ちを率直に話すことで、お子さんも「話してもいいんだ」「聞いてもらえるんだ」という安心感を持ちやすくなります。
5. 絵本や物語の世界を通じて感情について学ぶ
絵本や物語の登場人物は、実にさまざまな感情を豊かに表現してくれます。お子さんと一緒に読み進めながら、「この登場人物は、今どんな気持ちだと思う?」「もしも自分がこの立場だったら、どんな感情になるかな?」といった問いかけをすることで、お子さんは客観的な視点から感情について学ぶことができます。
絵本を使った感情学習の例
「うさぎさんが泣いているね。どうしてかな?悲しい気持ちなのかな、それとも痛い気持ちなのかな?」
「オオカミを見つけた時の子ブタさんたち、きっと心臓がドキドキして、怖い気持ちでいっぱいだったんだね」
物語の世界を通して、お子さんは自分自身の経験と照らし合わせながら、感情への理解をより深めることができます。
6. 言葉にできないお子さんの気持ちを「代弁・翻訳」してあげる
まだうまく言葉にできないお子さんの気持ちを、保護者の方が「翻訳」して代弁してあげることも、とても効果的なアプローチです。お子さんの表情や行動、状況から気持ちを推察し、それを言葉にして確認してあげましょう。
気持ちの翻訳・代弁の例
(下を向いて黙り込んでいる時)「もしかして、学校で何か心配なことや嫌なことがあったのかな?話したい気持ちになったら、いつでも聞くからね。話したくない時は、無理に言わなくても大丈夫だよ」
(妹にちょっかいを出してしまった時)「妹ちゃんにおもちゃを取られて、嫌な気持ちになったんだね。でも、手を出す代わりに、他の方法を一緒に考えてみようか。『貸して』って言ってみるのはどうかな?」
行動の背景にある本当の気持ちを汲み取って言葉にすることで、お子さんは「自分のことを分かってもらえた」「理解してもらえた」という安心感を得て、心の落ち着きを取り戻しやすくなります。
日々子供と向き合う、すべてのお父さん・お母さんへ
ここまでさまざまな方法をお伝えしてきましたが、どうか「全部を完璧にやらなければならない」と気負いすぎないでください。
お子さんの感情に丁寧に寄り添うことは、実はとてもエネルギーを要することです。時には、保護者の方だって疲れてしまったり、心に余裕がなくなってしまったりすることもあって当然です。そんな時は、お子さんのことだけでなく、ご自身の心のケアも忘れずに大切にしてください。
例えば、5分だけでも自分の好きな飲み物をゆっくりと味わって飲んでみたり、意識して深い呼吸を3回してみたり、「今日も本当によく頑張ったね」と自分自身をいたわる言葉をかけてあげたりしてください。
完璧な保護者である必要は、どこにもありません。保護者の方自身が心に少しでも余裕を持つことができれば、それが結果的にお子さんの安心感と心の安定につながっていくのです。
子供の感情表現に関してよくある質問
- うちの子は全く感情を外に出さないのですが、このまま大丈夫でしょうか?
-
感情表現の仕方や頻度には、生まれ持った気質をはじめとして、非常に大きな個人差があります。物静かで、感情が内側に向かいやすい性格のお子さんも確実にいらっしゃいます。まずは今回ご紹介したような関わり方を無理のない範囲で試していただきながら、お子さん一人ひとりのペースを温かく見守ってあげてください。
それでもご心配が続く場合は、一人で抱え込まずに、かかりつけの小児科医や、お住まいの地域の子育て支援センター、保健センターなどに相談してみることも、お子さんとご家族のために大切な選択肢の一つです。
- 嬉しい・悲しいなどの表現は苦手なのに、怒りや癇癪だけは激しく表現します。どのように対応したらよいでしょうか?
-
怒りや癇癪という形で現れる感情は、実は言葉にできない他の感情(悔しさ、悲しみ、不安、困惑など)が、適切な表現の場を見つけられずに爆発している状態かもしれません。
まずはお子さんとご自身の身の安全をしっかりと確保し、お子さんが少しずつ落ち着きを取り戻すのを、焦らずに待つことが大切です。そして、気持ちが安定してから「すごく嫌な気持ちだったんだね」「とても困った気持ちだったんだね」と、爆発の背景にある本当の気持ちを受け止めてあげる姿勢が重要になります。
- 何歳頃から感情表現の練習を始めたらよいのでしょうか?
-
実は、感情表現のサポートに「早すぎる」ということはありません。赤ちゃんの頃から、「あら、おなかが空いて不快だったのね」「眠くてぐずぐずしちゃうのね」といったように、お子さんの状態を言葉にして声をかけてあげることが、将来の感情表現の土台となります。
年齢が上がるにつれて、より複雑で微細な感情についても、少しずつ言葉にして教えてあげることができるようになります。
まとめ:子供の心に寄り添う温かなコミュニケーションを目指して
お子さんが自分の気持ちを言葉にできるようにサポートすることは、単純に表現力や語彙力を向上させるためだけのものではありません。
「自分の気持ちは、大切にされて当然のものなんだ」「自分の感情は、受け入れてもらえるものなんだ」
このように感じられる経験の積み重ねは、お子さんの自己肯定感を着実に育み、親子の間の信頼関係をより深く、より確かなものにしてくれます。そして、自分の気持ちを正確に理解し、相手に適切に伝えることができる力は、将来お子さんが豊かで充実した人間関係を築いていく上で、何にも代えがたい貴重な土台となることでしょう。
焦る必要は全くありません。お子さん一人ひとりが持つ個性やペースを大切にしながら、今日からできる小さな一歩を、ぜひ始めてみませんか。
きっと、お子さんの心に寄り添う温かな時間が、ご家族皆さんにとっての宝物となることでしょう。
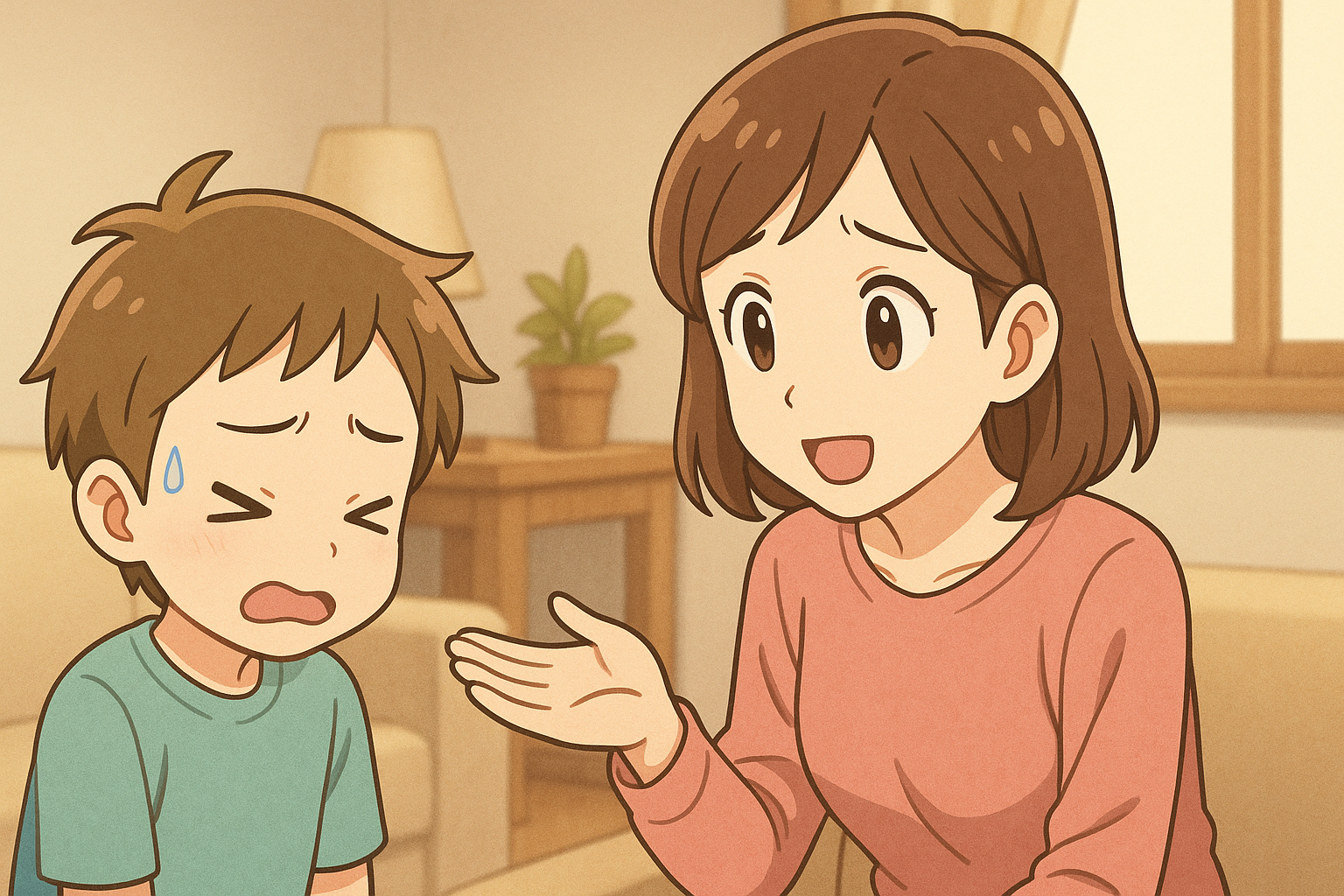
コメント