入院の連絡を突然受けると、「早くお見舞いに行きたいけど、何をどう準備すればいいのだろう…」と戸惑った経験はありませんか?
特に、お見舞いの封筒に関する作法には細かいルールがあり、意外に悩ましいものです。
「封筒のデザインが素敵だから、そのまま使ってもいいのかな?」
「名前を書くと見た目が台無しになりそうだけど…」
こうした声をよく耳にします。しかし、実はお見舞いの封筒に名前を書かないのは大きなマナー違反にあたります。
本記事では、封筒選びのポイントや正しい表書きの方法、内袋への記入の仕方、そして金額の相場まで、気になる疑問をすべて解説します。
さらに、お見舞いに行く最適なタイミングについても詳しくご紹介。マナーは相手への思いやりを伝える手段です。
「1日も早い回復を願う」という気持ちを、正しい形で表してみましょう。
なぜ封筒に名前を書くことが大切なのか
お見舞いは、病気やケガで入院している方に直接お渡しすることが多いもの。そのため「直接会うのだから、封筒にわざわざ名前を書く必要があるの?」と思う方もいるでしょう。
しかし、そこには大切な理由があります。
日本では、何かをいただいた場合、そのお礼をする習慣が根付いています。入院中の方には療養に集中していただきたいので「退院して落ち着いたらお返しをしよう」と考えることが一般的です。
もし封筒に名前が書かれていないと、誰からいただいたか分からなくなり、受け取った側を困らせてしまう可能性があります。
また、金額が不明だと適切なお返しが判断しにくくなります。
そのため、お見舞いの封筒には必ず以下を明記しましょう:
- 贈り主の氏名
- 金額
ここからは、お見舞いに必要な具体的マナーを順番に見ていきます。
お見舞い封筒の選び方:3つの重要ポイント
お見舞いは、病気やケガでの入院だけでなく、火災や災害時など困っている方へ気持ちを表す場面でも贈られます。
「早く元気になってほしい」「少しでも役立ててほしい」という想いを込めたものですが、その気持ちだけで十分かというとそうでもありません。
封筒の選び方ひとつとっても、一定のマナーを踏まえることが必要です。
選ぶ際には、以下の3点に注意してみてください。
水引の選択について
基本的には水引のない封筒がおすすめですが、もし水引付きのものを使う場合は「結び切り」または「あわじ結び」を選びましょう。
結び切りには「このような辛いことが二度と起こらないように」という意味が含まれています。
逆に「リボン結び」は「何度でも繰り返せる」という意味合いになるため、お見舞いには適しません。
色使いのポイント
封筒の色は紅白で統一するのが基本です(ご祝儀袋と同じ考え方)。
「お見舞いはおめでたいことではないから、紅白は派手では…?」と戸惑う方もいるかもしれません。
しかし、「早く元気になってほしい」という前向きな意味合いから、紅白が使われます。
黒白や黄色、銀色などは不幸事に使用されるので避けてください。
のしの有無
お見舞いの封筒には、のしを付けません。
のしはお祝い事で使われる縁起物です。お見舞いに限っては不向きなので注意してください。
書き方の基本:4つの重要ルール
封筒の種類が決まったら、次は書き方です。ここでも守るべきルールがいくつか存在します。
使用する筆記具と濃さ
表書きには毛筆や筆ペンを使うのが作法です。
ボールペンや万年筆を使うとカジュアルになりすぎるため、マナー違反と見なされることもあります。
どうしても筆ペンが用意できないときは、太字のフェルトペンなど、やや正式感を出せる筆記具を使いましょう。
濃い墨で書くのは、前向きな気持ちの表現でもあります。葬儀では突然のことを表すために薄い墨を使いますが、お見舞いでは「明るい気持ち」で臨む意味から、濃い墨がふさわしいのです。
表書きの書き方と位置
封筒の中央上段に表書きを書きます。
「御見舞い」や「お見舞い」と書きたくなるところですが、4文字は「死」を連想させると考えられる場合があるため、「御見舞」と3文字で書くことがおすすめです。
どんな状況(病気、事故、火事、災害など)でも「御見舞」で問題ありません。
氏名の正しい書き方
表書きの真下、中央にフルネームで記入します。
連名で贈る場合は以下を参考にしてください。
- 3名までなら全員の名前を記入
- 右から順番に地位や年齢が高い順
- 夫婦の場合は右側に夫のフルネーム、左側に妻の名前のみ
- 4人以上なら代表者の名前+「他一同」と書き、別紙にメンバーを同封
内袋への金額記入
内袋の表面中央には、縦書きで金額を記入します。このとき、新字ではなく旧字を用いることがポイントです。
理由は簡単に書き足されないようにするため。旧字を使うことで改ざんを防ぐ意味合いがあるのです。
| 通常の数字 | 旧字 |
|---|---|
| 1 | 壱 |
| 2 | 弐 |
| 3 | 参 |
| 5 | 伍 |
| 7 | 七 |
| 8 | 八 |
| 10 | 拾 |
| 100 | 百 |
| 1000 | 仟 |
| 10000 | 萬 |
「円」を「圓」と表記しても差し支えありません。
また、裏面には縦書きで住所を書くのが一般的ですが、封筒にあらかじめ記入欄がある場合は指示に従ってください。
お金の入れ方と金額の基準
封筒と筆記が整ったら、実際にお金を入れる段階です。気をつけたいポイントを確認しましょう。
お札の入れ方
綺麗な新札を使うのが望ましいですが、あらかじめ準備していた印象を与えたくない場合は、新札に一度折り目を付けるなど、ほどよい配慮をするとよいでしょう。
さらに、複数枚入れる場合はすべての向きを揃えて入れます。肖像画が表を向き、顔が上になるようにそろえるのが基本です。
金額の相場
お見舞いには、3,000円・5,000円・1万円など「奇数」が好ましいとされています。
相場は関係性によって異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。
| 関係 | 相場 |
|---|---|
| 親族・家族 | 5,000~10,000円を中心に状況に合わせて調整 |
| 友人 | 3,000~5,000円(親しさに応じて上下可能) |
| 職場関係 | 個人なら5,000円前後、複数で集めるなら1人3,000円程度 |
特に上司へのお見舞いは注意が必要です。現金を渡すことで「お金に困っているように見せてしまう」など、微妙な印象を与える恐れがあります。
会社の方針や慣例を確認しながら、現金ではなくクオカードやテレビカードなど、使いやすい金券を贈るケースも増えています。
それでも現金を贈りたい場合は「御伺い」と表書きし、一言添えることで失礼のない形にしましょう。
避けるべき数字
お見舞いの金額を決める際、4(死を連想)、6(無を連想)、9(苦を連想)などの数字は避けられることが多いです。
地域や宗教観によって考え方は変わる場合がありますが、一般的にはこれらを忌み数として敬遠します。
お見舞いのタイミングと心得
準備ができたら、実際にお見舞いに行くタイミングを考えましょう。
入院直後や手術前後は慌ただしく、検査の予定も立て込んでいるケースが多いので避けるのが賢明です。
- 面会時間を必ず事前に確認する
- 相手の都合を聞き、負担がかからない日時を選ぶ
- 挨拶をしたら短時間で済ませ、相手を疲れさせない
- 見舞金は手短に渡し、長居を控える
まとめ
お見舞いの封筒に関する主なポイントを整理すると、以下の通りです。
- 必ず氏名を記入して相手を困らせない
- 封筒は水引なしや結び切りの紅白で、のしは付けない
- 表書きは3文字で「御見舞」、墨は濃いものを使用
- 金額は改ざん防止のため旧字で書き、相手との関係性で額を決定
- 相手の体調を優先したタイミングで手短に渡す
一見細かいように感じるかもしれませんが、いずれも「相手を思いやる」ことから生まれた大切な作法ばかり。
正しいお見舞いマナーを押さえれば、「早く元気になってね」という気持ちがより相手に伝わりやすくなるはずです。
お見舞いの機会があれば、ぜひ今回ご紹介したポイントを思い出してみてください。きっとあなたの真心が届くことでしょう。
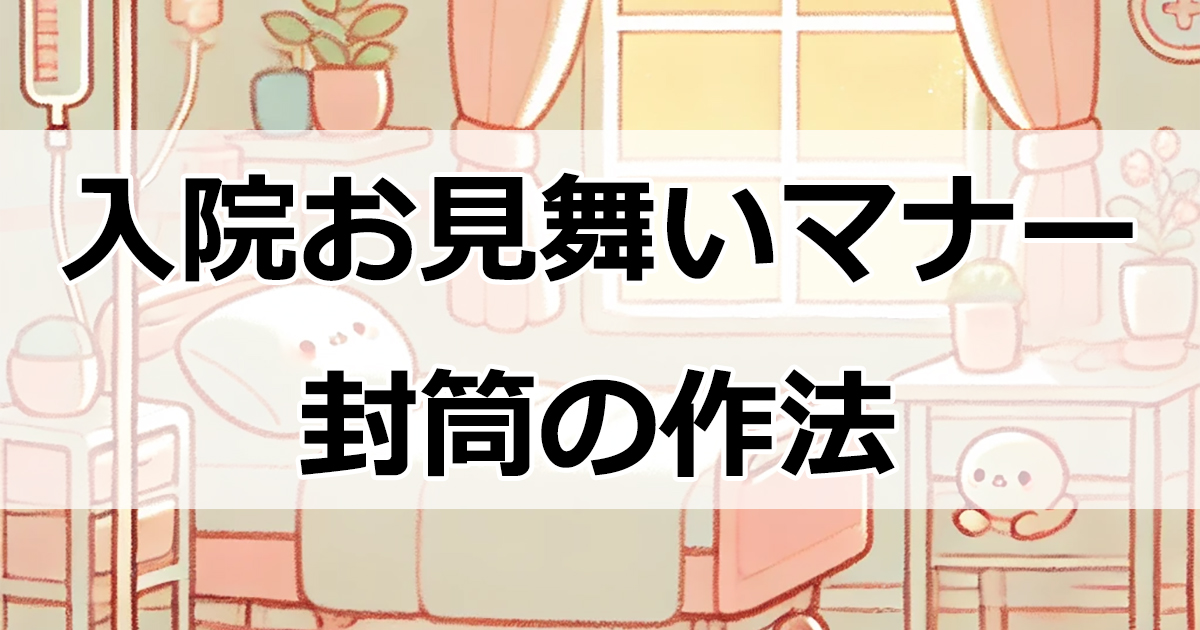
コメント