「読書感想文っていつも時間がかかって大変…」「子どもにどうやって書かせればいい?」と悩んでいる保護者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、小学校1年生・2年生のお子さんが無理なく取り組める読書感想文の書き方を詳しくご紹介します。
苦手意識を減らすポイントから具体的なサポート方法、構成例や実際の例文まで幅広くカバーしているので、ぜひ参考にしてみてください。
お子さんが自分で書けるようになるための工夫を取り入れつつ、夏休みの宿題をスムーズに終わらせましょう!
低学年の子どもにぴったりの読書感想文サポート法
夏休みの宿題で最後まで残りがちなのが「読書感想文」です。小学校1年生や2年生のお子さんにとっては、本を読むこと自体が大きなチャレンジ。そのうえ感想を文章にまとめるとなると、さらにハードルが上がるのも無理はありません。
実際、学校の授業で読書感想文の書き方をしっかり教えるケースは多くないため、保護者の方が「どう教えたらいいのかわからない…」と困ってしまうことも。ここでは、保護者の方ができるサポート方法を中心に解説します。
親はどこまで手伝うべき?学年別アドバイス
「手伝いすぎると自主性が育たないのでは?」という不安と、「でも全然書けないときはどうしたら…」というジレンマを抱える方は多いですよね。ここでは小学校1年生・2年生の段階でおすすめのサポートをまとめてみました。
小学校1年生の場合:
・一緒に声に出して本を読む
・どんなことを感じたのかを質問しながら引き出してあげる
・自分の言葉で言いにくい場合は、保護者が「こんなふうに思ったの?」と補ってみせる
小学校2年生の場合:
・まず子どもに本を読ませてみる
・詰まったら「どのシーンが面白かった?」など、具体的に質問して思考を促す
・書きたい内容をメモして整理する手伝いをする
子どもの性格や成長速度はそれぞれ異なります。早く文章を書き始める子もいれば、慣れるまで時間がかかる子もいます。「絶対に全部手伝ってはいけない」というわけでもなく、「何でもやってあげないとダメ」というわけでもありません。保護者の負担になりすぎない範囲で、子どもが「自分でできた!」という達成感を味わえるようにサポートしてあげましょう。
子どもが自分で書くためのステップバイステップガイド
小学校低学年の場合、読書感想文には厳密な書き方のルールがありません。大切なのは、「本を読んでどう感じたか」を子ども自身の言葉でまとめること。文字数や形式にこだわりすぎず、将来上の学年に進んだときの準備だと思って楽しみながら進めましょう。
おすすめの構成例は、以下のとおりです。
- タイトル(題名)
- どうしてその本を選んだのか
- 本のあらすじ(あってもなくてもOK)
- 心に残った場面と、その理由
- 読んで学んだことや今後に活かしたいこと
ポイントは「自分の生活や経験」と結びつけること。些細なことでもいいので、「自分ならこう思う」「自分はこういう体験をした」という部分を盛り込みましょう。初めての読書感想文なら、多少文章がたどたどしくても大丈夫。大切なのは、子ども自身の感性を大事にすることです。
「書けない…」とき、子どもから感想を引き出すコツ
いざ読ませてみても、「なんかよくわからない」「面白かったけど言葉にできない…」と困ってしまう子は少なくありません。その場合は会話形式で感想を引き出すのがおすすめです。
- 「どの場面がお気に入りだった?」
- 「主人公はどう思ったと思う?」
- 「自分だったらどうする?」
- 「この本を読んで気づいたことはある?」
こうした質問をすることで、子どもが頭の中で整理しやすくなります。出てきた答えを子ども自身にメモさせれば、そのメモがそのまま原稿用紙に書く内容になります。さらにメモを並べ替えるだけでも、立派な読書感想文の下書きができあがるでしょう。
それでも感想が思い浮かばない場合は、あらすじを書かせてみるのも手です。本の流れに沿って出来事を整理しているうちに、「あ、この場面はこう思ったかも!」と突然感想がひらめくこともあります。
小学校低学年向け読書感想文の構成と書き方
ここからは、より具体的に読書感想文の構成と書き方を解説します。低学年のお子さんには、あまり複雑な構成は必要ありません。以下の5ステップを意識するだけで、かなり書きやすくなるはずです。
- タイトル(題名)
- どうやってその本に出会い、なぜ選んだのか
- 簡単なあらすじ
- 気になった場面や印象に残った登場人物
- 読んで感じたこと、これからの目標
魅力的なタイトルのつけ方
タイトルはできれば感想文を書き終わってから考えたほうがスムーズです。先に本文を書いておくと、自分がどんなテーマに注目したかがわかりやすくなるからです。
テーマ別タイトル例:
| テーマ | タイトル例 |
|---|---|
| 友情 | 「ともだちっていいね!」 |
| 家族 | 「お父さん・お母さんへのありがとう」 |
| 動物 | 「大好きな犬との毎日」 |
| 挑戦 | 「ぼくがはじめてできたこと」 |
| 思いやり | 「やさしさをわすれないで」 |
もちろん「◯◯を読んで学んだこと」などのシンプルなタイトルもOK。長く考え込むよりは、少しでも面白そうだと思えるタイトルをつけるほうが子どものモチベーションにもつながります。
スムーズに書ける書き出しのテクニック
「どうやって書き始めればいいかわからない…」という子どもは多いです。書き出しのヒントとしては、「どうしてその本を選んだのか」を最初に書くのが簡単です。
書き出し例:
「わたしが『ぼくとわたしのほしぞら』を読んだのは、おばあちゃんにすすめられたからです。表紙にきれいな星空が描かれていて、とてもワクワクしました。どんな物語なのかなと思いながら読み始めました。」
「ぼくは『にじいろのさかな』を手に取ったとき、カラフルなうろこがとてもきれいだと思いました。さかなの絵本はあまり読んだことがないので、これを機に読んでみようと思いました。」
こんなふうに、本との出会いや表紙の印象を書くと文字数が稼げますし、読み手にも状況が伝わりやすくなります。
あらすじの簡単な書き方
あらすじ部分は、本の内容を短くまとめる箇所です。実は書かなくてもOKですが、文字数を増やしたいときや、感想が浮かばない子には「本の説明を書いてみて」と声をかけるとスムーズに筆が進むことが多いです。
ポイント:
- 登場人物の名前と大きな出来事を時系列で紹介
- 細かいエピソードすべてを書かなくても大丈夫
- 最後のオチや結末を完全には言わなくてもOK(ネタバレが気になる場合)
「この本は、主人公の〇〇ちゃんがある朝ふしぎな世界にまよいこむ話です。そこで××というキャラクターと出会い、いろいろな冒険をします」という形で、ざっくりとまとめましょう。
心に残った場面の効果的な表現法
読書感想文の中心は「どんな場面が印象に残ったのか」と「そのとき何を思ったのか」です。ここを具体的に書くことで、オリジナリティが出ます。
「わたしがいちばん印象に残ったのは、主人公が友だちと大げんかをしてしまう場面です。自分も友だちとケンカしたことがあるから、読んでいる間ずっとドキドキしました。」といった具合に、自分の体験や気持ちを交えて書くと説得力が増します。
また、「どうしてそれが印象に残ったのか」を書くのも忘れずに。「キャラクターの気持ちに共感した」「自分にも同じ経験があった」「想像以上に意外な展開だった」など、理由が明確になるほど読み手にも伝わりやすくなります。
印象に残るまとめの書き方
最後は感想文全体を締めくくる「まとめ」の部分です。書き方としては、「この本を読んでわかったこと」「これからどう行動したいか」を意識するとわかりやすいです。
まとめの例:
「この本を読んで、あきらめないことの大切さを学びました。わたしもときどき宿題をいやがってしまうけど、これからは少しずつでもがんばりたいと思いました。」
「ぼくは、主人公が勇気をもってチャレンジする姿に感動しました。これからは、苦手なことにも一歩ずつ挑戦してみようと思います。」
子どもなりの言葉で素直に「どう感じたか」を書ければ、それだけで十分に読み応えのある読書感想文になります。
低学年向け読書感想文例文集
ここでは小学校低学年の実例をイメージしたサンプル文をご紹介します。実際に子どもが書く際の参考にしてみてください。ただし、例文をそのまま写すのではなく、お子さんの言葉や体験を交えてアレンジすることが重要です。
例1:『ぐりとぐら』(1年生・およそ400字)
タイトル:「おおきなたまごをみつけたよ」
わたしは「ぐりとぐら」をよみました。おかあさんといっしょによんだので、むずかしいところもすぐわかりました。もりのなかでぐりとぐらがみつけたおおきなたまごをみて、わたしもびっくり。こんなにおおきなたまごでカステラをつくったら、おなかいっぱいになりそうだとおもいました。
わたしはおかあさんといっしょにカステラをつくったことがあります。ぐりとぐらみたいに、おいしいおかしができたときはとてもたのしかったです。だからこの本をよんで、またいっしょにつくりたいなと思いました。いつかもっとおおきなたまごをみつけたら、みんなでわけあって食べたいです。
例2:『はじめてのおつかい』(1年生・およそ500字)
タイトル:「ひとりでチャレンジ」
ぼくが「はじめてのおつかい」を読んだのは、おかあさんにすすめられたからです。みいちゃんがはじめておつかいにいくお話ですが、ぼくもはじめてひとりでコンビニにいったときを思いだしました。
みいちゃんは、おかあさんにたのまれてお店までいきますが、とちゅうでころんだり、おつりをわすれたりといろいろたいへんそうでした。ぼくもおかしを買うとき、うまくお金をわたせるかどきどきしました。
さいごはみいちゃんがちゃんと帰ってこれたので、ほっとしました。ぼくも、いまはひとりで外にいくのはちょっとこわいけど、がんばればできるんだなと思いました。これからはもっといろんなことにチャレンジして、自分の力でできるようになりたいです。
例3:『おおきなかぶ』(2年生・およそ600字)
タイトル:「みんなでちからをあわせるとすごい!」
わたしは「おおきなかぶ」をよみました。おじいさんがかぶをそだてて、とてもおおきくなったけどひっぱってもぬけなくて、おばあさんやまご、いぬやねこまでよんで、さいごにねずみがちからをかしてくれて、ようやくかぶがぬけます。
わたしがとくにすごいと思ったのは、ちいさなねずみがいがいなかぎやくになっていることです。大きなおじいさんやたくさんの人ががんばってもだめだったのに、ねずみがくわわったとたんにぬけたから、チームワークってたいせつなんだなあと感じました。
このまえ、わたしのクラスで運動会のつなひきをしたときも、はじめはちからが足りなくてまけそうになりました。でも、声をかけあっておもいきりひっぱったら、逆てん勝ちできました。
この本をよんで、みんなで協力することのたいせつさをあらためてわかりました。これからも、友だちといっしょにちからをあわせて、むずかしいことでもあきらめずにチャレンジしていきたいです。
まとめ:楽しみながら書く読書感想文のコツ
小学校低学年にとって読書感想文は、文章を書く第一歩になる重要な機会です。とはいえ、はじめから上手に書かなくてもかまいません。むしろ「本を読むって楽しい」「ちょっとだけでも自分の気持ちを文章にできた」と感じられるほうが大切です。
保護者の方は「どこまでサポートするか」に迷うかもしれませんが、子どもの特性や成長段階にあわせて柔軟に手伝ってあげるとよいでしょう。どんなふうに感じたのかを引き出してあげる質問やメモの取り方など、ちょっとしたコツを使えば、自宅でもラクに文章をまとめる練習ができます。
ぜひ、親子で楽しみながら読書感想文に取り組んでみてください。時間に追われて「早くやりなさい!」と焦る気持ちになることもあるかもしれませんが、いっしょに本を読んだり話し合ったりする時間は、お子さんにとってかけがえのない思い出になるはずです。少しでも負担を減らしつつ、「本っておもしろい」「書くことっておもしろい」と感じられるきっかけを作ってあげましょう。
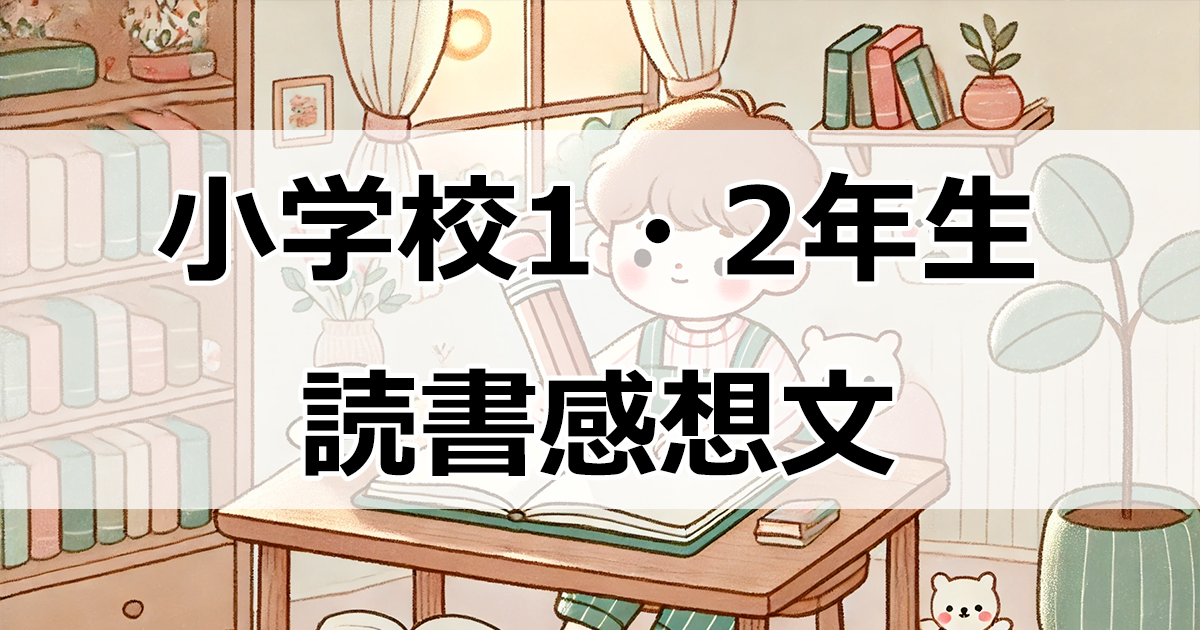
コメント