「もう時間がないから私がやっちゃおう…」「ちゃんとできているか心配で、つい口を出してしまう…」
お子さんのことを大切に思うからこそ、つい先回りして手伝ってしまったり、細かく指示を出してしまったりすることってありますよね。でも、後になって「あの時は見守ってあげれば良かったな」と後悔することも多いのではないでしょうか。
子どもの将来を考えると自立してほしいけれど、日々の忙しさの中では理想通りにいかないもの。そんな葛藤を抱えているのは、お子さんのことを真剣に考えている証拠だと思います。
この記事では、「ついつい手を出してしまう」というお悩みを抱えている親御さんに向けて、子どもの「やってみたい!」「できた!」という気持ちを大切にしながら、自立心を自然に育んでいく関わり方をご紹介します。明日からすぐに実践できる具体的なコツも満載です。
なぜ子どもの自立心を育むことが大切なのか
まず、なぜ子どもの自立心を育てることがそんなに重要なのかを考えてみましょう。
自立心がある子どもは、新しいことに挑戦する意欲が高く、困難に直面しても諦めずに取り組む力を持っています。また、自分で考えて行動する習慣が身につくため、将来的に自分らしい人生を歩んでいけるようになります。
一方で、いつも親に頼って生活していると、「自分にはできない」という意識が強くなってしまいがちです。親がいないと何もできない、失敗を極端に恐れるといった傾向が出てくることもあります。
でも大丈夫です。自立心は一朝一夕で身につくものではありませんし、親の関わり方を少し工夫するだけで、お子さんの中にある「自分でやってみたい」という気持ちを伸ばしていくことができますよ。
子どもの自立心を育む2つの重要な要素
子どもの自立心を健やかに伸ばしていくために、特に大切にしたい要素が2つあります。
小さな達成感の積み重ね
「自分でできた!」という成功体験は、子どもにとって何よりの栄養です。たとえ大人から見れば些細なことでも、子どもにとっては大きな挑戦。靴下を一人で履けた、お皿を運べた、自分で服を選べたといった小さなことでも、しっかりと認めてあげることで、次への意欲につながります。
安心できる環境づくり
「失敗しても大丈夫」「パパもママも味方だよ」という安心感があってこそ、子どもは新しいことに挑戦する勇気を持てます。失敗したときに叱られるのではなく、「頑張ったね」「次はどうしてみる?」と言ってもらえる環境があれば、子どもは失敗を恐れずにチャレンジできるようになります。
この記事でご紹介する関わり方は、すべてこの2つの要素を大切にした内容になっています。
発達段階に合わせた関わり方のポイント
子どもの発達には個人差がありますが、年齢に応じた大まかな特徴を理解しておくと、より適切な関わりができるようになります。
幼児期(3歳から5歳頃)の関わり方
この時期の子どもは「自分でやりたい!」という気持ちがとても強くなります。イヤイヤ期を経て、自我がはっきりと芽生える大切な時期です。
時間はかかるし、完璧ではないかもしれませんが、まずは子ども自身にやらせてみることが一番大切です。
お着替えの場面では、時間に余裕がある時は「自分でやってみる?」と声をかけて、まずは挑戦させてあげましょう。
ボタンが難しそうなら「一緒にやってみようか」と手を添える程度にとどめます。
たとえ服が裏返しでも、まずは「一人でお着替えできたね!すごいじゃない!」と挑戦したことそのものを褒めてあげてください。
簡単なお手伝いをお願いするのもおすすめです。
「おもちゃさんをお家に帰してもらえるかな?」「お箸を並べるお手伝いをお願いします」など、子どもでもできそうなことを具体的にお願いしてみましょう。
お手伝いをしてもらったら「ありがとう、助かったよ!」と感謝の気持ちを伝えることで、子どもは自分が役に立っているという実感を得られます。
学童期(6歳以降)の関わり方
小学生になると、論理的に考える力が育ってきます。親が指示するだけでなく、子ども自身に考えさせ、選択させる機会を意識的に作ることが重要になります。
指示の仕方を工夫してみましょう。
「宿題をしなさい」ではなく「今日の宿題は、夕ご飯の前にやる?それとも後にやる?」と選択肢を提示します。
「どうしてその時間にしたいの?」と理由も聞いてみると、子どもは自分なりに考える習慣が身につきます。
日常の小さな決定も、できるだけ子どもに委ねてみてください。
明日着る服を前の晩に選んでもらったり、休日の過ごし方について家族で話し合ったりする機会を作りましょう。
子どもの意見を聞いて「なるほど、そう考えたんだね」と受け止めることで、自分の考えが尊重されているという実感を持てます。
失敗した時の対応も大切なポイントです。
忘れ物をしてしまった時、すぐに学校に届けるのではなく「今度はどうしたら忘れずに済むかな?」と一緒に対策を考えてみましょう。
失敗を責めるのではなく、次に活かすための学びの機会として捉えることで、子どもは失敗を恐れずに行動できるようになります。
日常生活で実践!具体的な声かけ例
毎日の生活の中には、子どもの自立心を育むチャンスがたくさん隠れています。具体的なシーンを想定して、どんな声かけをすると良いのかを見ていきましょう。
朝の準備での関わり方
朝は時間がないからこそ、つい手を出してしまいがちですが、少しの工夫で子どもの自立を促すことができます。
シーン:子どもが靴下を履こうと頑張っているけれど、うまくいかずに時間がかかっている
あまり良くない対応例:「もう時間がないから、お母さんがやってあげる!貸して!」
このような声かけでは、子どもは「自分にはできないんだ」と感じてしまい、次回も最初から親に頼るようになってしまう可能性があります。
おすすめの対応例:「かかとさんが入らなくて困ってるね。でも、ここまで自分で頑張ったのはすごいよ!」
まずは子どもが頑張った部分を具体的に褒めてあげましょう。その上で「少しだけ一緒にやってみようか」と提案して、あくまでお手伝いする立場で関わります。
片付けの場面での関わり方
片付けは、責任感や整理整頓の習慣を身につける大切な生活スキルです。
シーン:遊んだ後のおもちゃがそのままになっていて、なかなか片付けようとしない
あまり良くない対応例:「どうして片付けないの!いつもそうなんだから!早くしなさい!」
このような叱り方では、片付けが嫌なことだと印象づけてしまい、自主的に行動する気持ちを削いでしまいます。
おすすめの対応例:「おもちゃさんたちが、お家(箱)に帰りたがってるよ。一緒に送ってあげようか」
擬人化することで、片付けが楽しい活動に変わります。「お母さんと競争してみる?どっちが早くお片付けできるかな」とゲーム感覚を取り入れるのも効果的です。
片付けが終わったら「お部屋がきれいになって気持ちいいね」と、片付けた後の爽快感を一緒に味わいましょう。
宿題や勉強での関わり方
学習習慣を身につけることは、将来の自立にとても重要です。
シーン:宿題をなかなか始めようとしない
あまり良くない対応例:「まだ宿題やってないの?早くやりなさい!」
命令口調では、勉強が義務的なものになってしまい、自主的に取り組む気持ちが育ちません。
おすすめの対応例:「今日の宿題は何があるの?どれから始める?」
まずは宿題の内容を一緒に確認して、子ども自身に順番を決めさせてあげます。「算数から?それとも漢字から?」と選択肢を提示することで、子どもは自分で決めたという実感を持てます。
集中して取り組めたら「集中して頑張ったね。字もとても丁寧に書けているよ」と、努力した過程を具体的に褒めてあげましょう。
要注意!無意識に自立を妨げてしまう親の行動
子どものためを思ってしていることが、実は自立心の成長を阻んでしまっている場合があります。以下のような行動をしていないか、一度振り返ってみてください。
1. 先回りしすぎてしまう
子どもが困りそうだと予想して、事前に何でも準備してしまったり、問題を解決してしまったりしていませんか。
「転ばないように」と常に手を引いたり、「忘れ物をしないように」と毎朝持ち物をチェックして準備してしまったりすると、子どもは自分で気をつけたり、準備したりする機会を失ってしまいます。
適度な失敗は、子どもにとって大切な学習の機会です。安全面に配慮しながらも、子どもが自分で経験して学べるような環境を作ってあげることが大切です。
2. 結果だけに注目してしまう
「100点取れてすごいね」「1位になれなくて残念だったね」など、結果だけに注目した言葉かけをしていませんか。
結果だけを評価されると、子どもは失敗を極端に恐れるようになったり、良い結果が出ない時に自分はダメだと思い込んでしまったりします。
「毎日コツコツ練習したから、こんなに上手になったんだね」「最後まで諦めずに頑張ったね」など、努力の過程や取り組む姿勢を認める言葉を意識して使うようにしましょう。
3. 他の子と比較してしまう
「お兄ちゃんの時はもっと早くできたのに」「○○ちゃんはもう一人でできるよ」など、他の子と比較する言葉は、子どもの自己肯定感を傷つけてしまいます。
子どもはそれぞれ個性があり、成長のペースも違います。比べる相手は他の誰でもなく、「昨日のその子自身」です。「昨日よりも上手にできるようになったね」「前はできなかったけど、今はこんなことができるようになったんだね」と、その子なりの成長を認めてあげましょう。
4. 子どもの気持ちを否定してしまう
子どもが何か意見を言った時、「でも」「だって」「そんなこと言わないの」などと、すぐに否定していませんか。
自分の気持ちを否定されると、子どもは自分の考えに自信を持てなくなってしまいます。まずは「そう思うんだね」「そんな気持ちなんだね」と、一度受け止めてあげましょう。その上で「お母さんはこう思うよ」と、親の考えを伝えれば良いのです。
5. 失敗を必要以上に心配してしまう
「危ないからやめなさい」「失敗したらどうするの」と、親が不安を表に出しすぎると、子どもは新しいことに挑戦することを怖がるようになってしまいます。
もちろん安全面への配慮は必要ですが、適度なリスクは子どもの成長には欠かせません。「気をつけてやってみてね」「失敗しても大丈夫だよ」というメッセージを伝えながら、子どもの挑戦を応援してあげましょう。
兄弟姉妹がいる場合の特別な配慮
兄弟姉妹がいるご家庭では、それぞれの子どもの発達段階や個性に応じた関わりが必要になります。
上の子には年齢相応の責任を与えながらも、「お兄ちゃんなんだから」「お姉ちゃんでしょ」という言葉で過度に頑張らせすぎないよう注意しましょう。下の子には、上の子と比較するのではなく、その子なりのペースを大切にしてあげることが重要です。
また、兄弟間で得意なことが違うのは当然です。それぞれの個性を認めて、「○○君は絵を描くのが上手だね」「○○ちゃんは優しいところがすてきだね」と、それぞれの良いところを具体的に褒めてあげましょう。
親自身の心のケアも忘れずに
子どもの自立を支援するためには、親自身が心身ともに健康で、余裕を持って子どもと向き合えることが大切です。
完璧な親になろうとする必要はありません。10回中9回は思うようにいかなくても、1回でも「見守ることができた」「子どもの気持ちを受け止められた」ということがあれば、それは大きな前進です。
忙しい毎日の中でも、たまには自分だけの時間を作って、好きなことをしたり、リラックスしたりする時間を大切にしてください。親がストレスを溜め込んでいると、どうしても子どもに対してイライラしやすくなってしまいます。
また、パートナーや家族、友人など、周りの人に相談したり、愚痴を聞いてもらったりすることも大切です。一人で抱え込まずに、周りの人のサポートを積極的に活用しましょう。
今日から始められる実践チェックリスト
最後に、今日からすぐに実践できる具体的なアクションをまとめました。全部を一度にやろうとせず、できそうなものから少しずつ始めてみてください。
基本的な心構え
□ 子どもが何かに挑戦している時は、まず見守ってみる
□ できた部分を具体的に褒める言葉を一日一回は使う
□ 「ダメ」「早く」などの否定的な言葉を言いそうになったら、一呼吸置く
日常生活での工夫
□ 朝の支度で、一つでも子どもに任せる部分を作る
□ 簡単なお手伝いを具体的にお願いしてみる
□ 指示ではなく、選択肢を提示する声かけを心がける
□ 子どもの意見を聞く時間を意識的に作る
失敗への対応
□ 失敗した時は「大丈夫」と最初に声をかける
□ 「次はどうしようか」と一緒に改善策を考える
□ 結果よりも努力した過程を認める言葉をかける
親自身のケア
□ 完璧を目指さず、小さな成功を認める
□ イライラした時は深呼吸して、一息つく
□ 週に一度は自分のための時間を作る
まとめ:子どもの力を信じて、そっと見守る勇気を
子どもの自立心を育てるということは、親が何かを「してあげる」ことではありません。子どもが元々持っている「成長したい」「自分でやってみたい」という気持ちを信じて、それをそっと後押ししてあげることなのです。
時には失敗することもあるでしょうし、思うようにいかないこともたくさんあると思います。でも、その一つひとつが子どもにとって大切な学びの機会になります。
焦る必要はありません。お子さんのペースに合わせて、「できた!」という小さな成功体験を積み重ねていけるよう、温かく見守ってあげてください。
親御さんの愛情のこもった関わりが、お子さんが将来自分らしい人生を歩んでいくための、何よりも大きな力になるはずです。
子育てに正解はありませんが、お子さんのことを想う気持ち
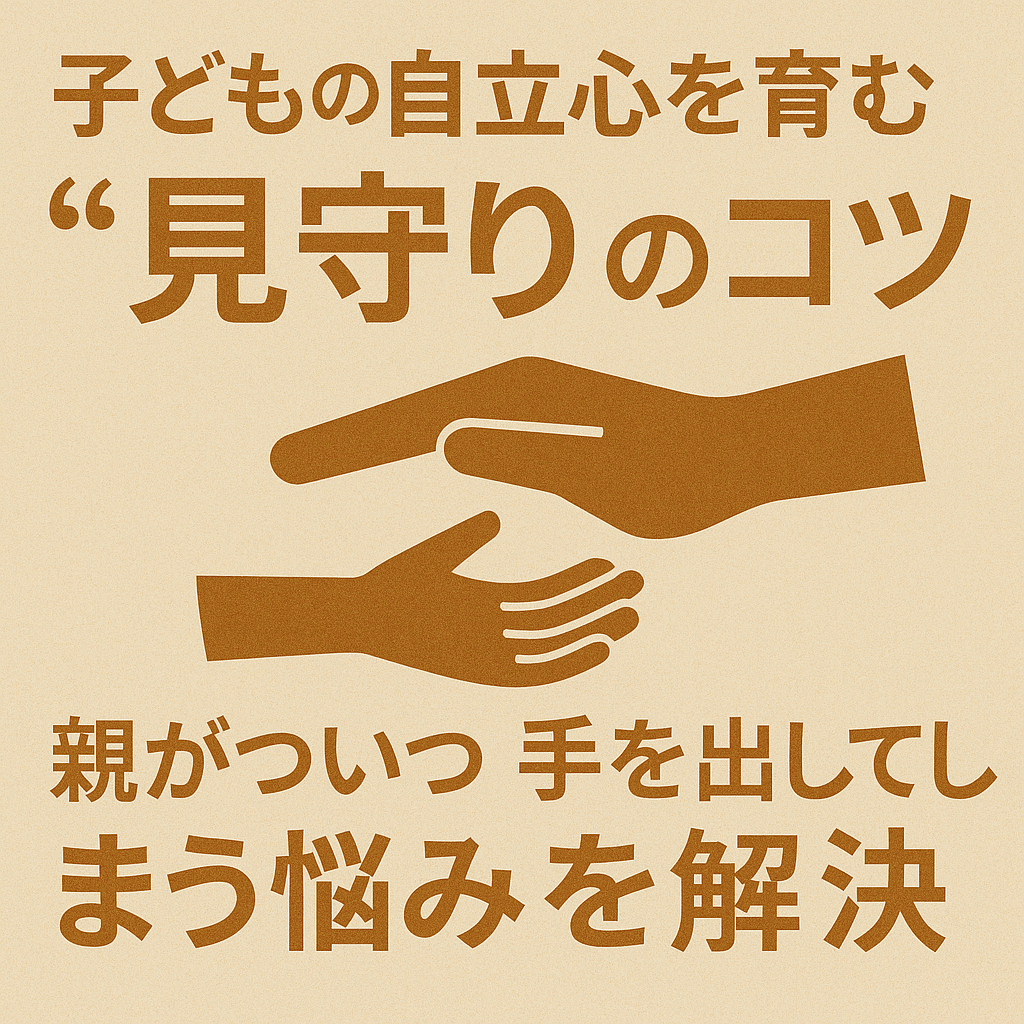
コメント