寒い季節になると、窓からの「ヒュー」という音とともに感じる冷たい風。その正体は、アルミサッシからの隙間風です。この厄介な問題は、単に寒さをもたらすだけでなく、冷暖房効率の低下による光熱費の増加にもつながります。実は、住宅の熱損失の約20~30%は窓から生じているといわれています。
本記事では、アルミサッシからの隙間風が発生する原因を詳しく解説し、自分でできる診断方法から、即効性のある対策、さらにはプロに依頼すべきケースまで、幅広く解説します。DIYで簡単にできる対策から、季節ごとのメンテナンス方法まで、これを読めばアルミサッシの隙間風問題をスムーズに解決できるでしょう。
アルミサッシの隙間風はなぜ起きる?
アルミサッシからの隙間風は、複数の要因が重なって発生します。主な原因を理解することで、効果的な対策を講じることができます。
フレームの経年変化をチェックするポイント
アルミサッシのフレームは、年月が経つにつれて少しずつ変形することがあります。これはアルミニウムの特性と、建物自体のわずかな歪みによるものです。以下のポイントをチェックして、フレームの経年変化を確認しましょう。
- サッシの四隅に隙間がないか目視で確認する
- 窓を閉めた状態で、フレームと窓の間に均等な隙間があるか確認する
- 窓を開閉したときに引っかかりや抵抗を感じるか
- フレームに目に見える歪みや変形がないか
特に築10年以上の住宅では、建物全体の微妙な沈下によってフレームに歪みが生じやすくなります。また、地震や強風の影響で少しずつ変形することもあります。
パッキンの劣化サインを見つける方法
アルミサッシの気密性を保つ上で重要な役割を果たすパッキン。このゴム製のパーツは経年劣化によって弾力を失い、隙間風の原因となります。以下のサインがあれば、パッキンの劣化が疑われます。
- パッキンが硬化して弾力性を失っている
- ひび割れや欠けがある
- 色が変色している(黒→灰色や白色)
- 触るとポロポロと粉が出る
- 部分的に剥がれている
パッキンの寿命は一般的に7~10年程度とされていますが、直射日光が当たる南向きの窓や、湿気の多い浴室などでは劣化が早まる傾向があります。定期的なチェックが重要です。
戸車・レールが原因になるケースとは?
引き違い窓の下部にある戸車(ローラー)とレールも、隙間風の原因になり得ます。以下のような状況では、戸車やレールが原因で気密性が損なわれている可能性があります。
- 窓の開閉がスムーズでない(引っかかる、重い)
- 窓の高さにバラつきがある(水平に閉まらない)
- レールに汚れや異物が溜まっている
- 戸車が摩耗または破損している
- レールが変形している
戸車の調整不良は、窓全体の高さや角度に影響し、上部や側面に隙間を生じさせます。特に、寒い時期に隙間風を感じるようになった場合は、戸車の状態をチェックする価値があります。
引用元:国土交通省 住宅性能表示制度ガイドライン(2023年7月改定)
自宅で簡単にできる気密診断方法は?
専門業者に依頼せずとも、自宅で簡単に窓の気密性を診断する方法があります。以下に紹介する方法を使えば、どこから隙間風が入ってくるのかを特定できます。
紙テストで隙間風を判定する手順
最も手軽な方法が「紙テスト」です。A4用紙一枚あれば、窓の気密性を簡単にチェックできます。
- 窓を一度完全に閉める
- A4用紙を半分に折る
- 折った紙を窓のさまざまな部分に挟み込む
- 紙を引っ張ってみて、抵抗なく引き抜けるかを確認する
紙が簡単に引き抜ける場所は、気密性が低く隙間風が入りやすい部分です。特に窓の四隅や、サッシとガラスの間、引き違い窓の場合は窓と窓の間の部分を重点的にチェックしましょう。この方法は風のない日でも実施可能で、隙間の場所を正確に特定できるメリットがあります。
スマホの温度計アプリを活用するコツ
スマートフォンの温度計アプリやサーモグラフィーアプリを活用すれば、より視覚的に隙間風の侵入箇所を特定できます。特に寒い日に効果的です。
- 温度計アプリをダウンロードする(無料のものも多数あります)
- 室内の暖房を入れて、室内外の温度差を作る
- 窓の周囲をアプリで測定し、温度が急激に下がる箇所を探す
温度差が5℃以上ある箇所は、隙間風が入っている可能性が高いと判断できます。また、最近のスマートフォンには赤外線センサーを搭載したモデルもあり、それらを使えば簡易的なサーモグラフィー撮影も可能です。温度変化を色で視覚化できるため、家族と一緒に楽しみながら隙間探しができるでしょう。
専門機器(気流計)を使うメリット
より正確に隙間風を検出したい場合は、気流計(風速計)の使用がおすすめです。ホームセンターやオンラインショップで5,000円前後から購入できる手持ち式の気流計があります。
- 風速を数値で確認できるため、客観的な判断が可能
- 微弱な気流も検出できるため、目に見えない隙間風も発見可能
- 対策前後の効果測定にも使える
- 複数の窓を比較して、優先的に対策すべき窓を特定できる
気流計を使う際は、風の無い穏やかな日を選びましょう。また、エアコンや換気扇を停止させて、人工的な気流の影響を排除することが大切です。測定値が0.5m/秒以上の場所は、隙間風対策が必要と判断できます。
引用元:住宅省エネ2023キャンペーン公式サイト(2023年4月)
隙間テープでスピード対策するコツは?
隙間が特定できたら、まず試したいのが隙間テープによる対策です。手軽で費用も抑えられる上、即効性があります。ただし、素材選びや貼り方によって効果に大きな差が出るため、以下のポイントを押さえておきましょう。
素材別(EPDM・ウレタン)の選び方
隙間テープには主に2種類の素材があり、用途によって使い分けることで効果を最大化できます。
- EPDMゴム製テープ
- 天然ゴムの一種で耐久性に優れている
- 弾力性があり、多少の凹凸にも対応可能
- 耐候性・耐紫外線性が高く、屋外での使用に適している
- 比較的硬めで、隙間が1mm前後の場所に最適
- 価格は比較的高め(1巻500~1,000円程度)
- ウレタンフォーム製テープ
- 柔らかく、圧縮されても復元力がある
- 断熱性・防音性に優れている
- 隙間の大きさに合わせて様々な厚みが選べる(2mm~10mm程度)
- 比較的安価(1巻300~800円程度)
- 経年劣化で硬化しやすいため、1~2年ごとの交換が推奨
基本的には、小さな隙間にはEPDMゴム製、大きめの隙間や凹凸のある場所にはウレタンフォーム製を選ぶのがおすすめです。また、両面テープ付きのタイプを選べば、貼り付けが簡単になります。
貼付け位置を決める簡単ガイド
隙間テープを貼る位置によって、効果や美観が大きく変わります。最適な貼り付け位置を決めるためのガイドラインです。
- 引き違い窓の場合:
- 窓とサッシの接触部分(主に縦の辺)
- 上下のレールと窓の接触部分
- 窓と窓がぶつかる中央部分
- 開き窓の場合:
- 窓の外周全体のフレームに沿って
- 特に窓の下部(雨水が侵入しやすい部分)
- すべての窓に共通:
- 気流計や紙テストで隙間が特定された部分
- 窓を閉めたときに光が漏れている部分
見た目を重視する場合は、窓を閉めた状態で外から見えない位置に貼ることがポイントです。また、窓の開閉の邪魔にならない位置を選ぶことも重要です。テープを貼る前に、実際に窓を開閉して動きを確認しておきましょう。
長持ちさせる貼り付け前の下処理
隙間テープの効果を長持ちさせるためには、貼り付け前の下処理が重要です。以下の手順に従って、しっかりと下準備をしましょう。
- 清掃:アルコールや中性洗剤を使って貼付け面の油脂や汚れを完全に除去する
- 乾燥:貼付け面を完全に乾かす(ドライヤーで軽く温めると接着力アップ)
- 下地処理:特に劣化したアルミ面には、プライマーを薄く塗布すると密着性が向上
- 適切な長さ:一度に長いテープを貼るのではなく、30cm程度ずつ小分けにして貼る
- 圧着:貼り付け後、指やローラーでしっかり圧着する
また、気温が10℃以下の日は接着力が弱まるため、暖かい日中に作業するのがおすすめです。テープを貼る前に、窓を開閉して動きをチェックし、開閉の妨げにならないよう計画しましょう。適切に貼れば、EPDMタイプで2~3年、ウレタンタイプでも1~2年の効果が期待できます。
引用元:JIS A 1518 気密材規格(2022年改定)
パッキンを交換する手順と選択基準は?
隙間テープでは対応しきれない場合や、根本的な解決を望む場合は、パッキンの交換を検討しましょう。パッキンはアルミサッシの気密性を保つ重要な部品で、適切に交換すれば隙間風問題を大幅に改善できます。
パッキンの型番を調べるスムーズな方法
パッキンを交換するためには、まず適合する型番を調べる必要があります。以下の方法で効率的に型番を特定できます。
- メーカー名の確認:サッシのフレームやガラス部分に刻印されていることが多い(LIXIL、YKK AP、三協アルミなど)
- 型番の確認:
- サッシ内部や側面に小さく刻印されている
- 住宅の引き渡し書類や取扱説明書に記載されていることもある
- サイズ測定:
- 現在のパッキンの幅と厚さをノギスやメジャーで測定
- 形状(リップ形状、くさび形状など)も確認
- 製造年の確認:窓の製造年代によって使用されるパッキンが異なる場合がある
型番が分からない場合は、古いパッキンのサンプル(5~10cm程度)を取り外して持参し、ホームセンターや建材店で相談するのも効果的です。また、各メーカーのお客様相談センターに問い合わせれば、写真を送ることで適合品を教えてもらえる場合もあります。
安全に外す・取り付けるための道具
パッキンの交換作業は、適切な道具を使うことで安全かつスムーズに行えます。以下の道具を準備しましょう。
- 基本工具:
- マイナスドライバー(パッキン引き抜き用)
- ゴムハンマー(軽く叩いて固定するため)
- カッターナイフ(パッキンの切断用)
- メジャー(長さ測定用)
- 専用工具:
- パッキン挿入ローラー(ホームセンターで500円程度)
- 隙間ゲージ(隙間の幅を正確に測るため)
- クリーニング用品:
- アルコールクリーナー(溝の清掃用)
- ブラシ(細かい汚れ除去用)
- マスキングテープ(作業範囲の保護用)
これらの道具に加え、新しいパッキンをスムーズに挿入するためのシリコンスプレーも用意しておくと作業がしやすくなります。また、手を保護するための軍手や、床を傷つけないための養生シートも準備しておくと安心です。
交換手順
パッキンの交換は以下の手順で行います:
- 準備:窓を全開にし、作業スペースを確保する
- 古いパッキンの除去:
- マイナスドライバーの先で古いパッキンの端を浮かせる
- 浮いた部分を指でつまみ、溝に沿って慎重に引き抜く
- 途中で切れた場合は、再度端部を浮かせて引き続き
- 溝の清掃:
- アルコールクリーナーとブラシで溝内部の汚れを徹底的に除去
- 乾いた布で拭き取り、完全に乾燥させる
- 新しいパッキンの取り付け:
- パッキンは必要な長さより少し長めに切る(後で調整可能)
- パッキンの端を溝の角から挿入し始める
- パッキン挿入ローラーで少しずつ溝に押し込む
- 角の部分はゆっくりと丁寧に押し込む
- 調整と仕上げ:
- 全体を挿入後、余分な部分をカッターナイフで切り落とす
- 接合部はできるだけ目立たない位置(上部や角)にする
- ゴムハンマーで軽く全体を叩き、しっかり固定する
交換後に気密性能を確認するチェックリスト
パッキン交換後は、以下のチェックリストで気密性能を確認しましょう。
- 窓をゆっくり開閉し、スムーズに動くか確認
- 窓を閉めた状態で、パッキンが均等に圧縮されているか確認
- 紙テストを再度実施し、隙間風が改善されたか確認
- 雨の日に雨水の侵入がないか確認
- 冷暖房使用時の室温保持状況を確認
これらのチェックで問題が見つかった場合は、パッキンの挿入が不十分な可能性があります。再度確認し、必要に応じて調整や再挿入を行いましょう。適切に交換できていれば、窓の開閉感触が改善され、隙間風も大幅に減少しているはずです。
引用元:LIXIL 公式メンテナンスマニュアル(2024年2月版)
戸車調整で開閉を軽くする方法は?
窓の開閉がスムーズでない場合、戸車(ローラー)の調整が必要かもしれません。戸車の調整は、窓の位置を正しく合わせて気密性を高めるだけでなく、開閉もスムーズにする効果があります。
戸車の高さを合わせるプラスドライバー操作
戸車の高さ調整は、ほとんどの場合プラスドライバーで行います。以下の手順で簡単に調整可能です。
- 調整ネジの場所を確認:
- 引き違い窓の場合、下枠の両端付近に調整ネジがある
- 通常は小さな穴が開いており、その中に調整ネジがある
- 窓の状態確認:
- 窓を閉めた状態で上部の隙間が均等か確認
- 窓を少し開けた状態で、サッシとの隙間を確認
- 調整方法:
- 右回し(時計回り):窓が上に上がる
- 左回し(反時計回り):窓が下に下がる
- 微調整のコツ:
- 一度に大きく回さず、4分の1回転ずつ調整
- 調整後は必ず窓を開閉して感触を確認
両側の戸車が均等に調整されていないと、窓が傾いて隙間風の原因になります。両側をバランスよく調整することが重要です。また、調整ネジが固くて回らない場合は、サビ落としスプレーを少量塗布してから再度試みましょう。
滑りを良くする潤滑スプレーの選択
戸車や窓のレールには、適切な潤滑剤を使用することで開閉をスムーズにし、結果的に気密性も向上させることができます。最適な潤滑剤を選ぶポイントを解説します。
- シリコンスプレー:
- 最もおすすめの潤滑剤
- ホコリを吸着しにくい
- 長期間効果が持続する
- プラスチック部品にも安全
- フッ素系スプレー:
- 高い潤滑効果
- 水や汚れをはじく効果が高い
- やや高価(1,000円前後)
- 注意が必要な潤滑剤:
- オイルスプレー:ホコリを吸着しやすい
- グリス:窓のレールには不向き(重くなる)
- CRCなどの強力な潤滑スプレー:プラスチック部品を傷める可能性あり
潤滑剤の使用方法も重要です。まず、レールや戸車の溝をブラシなどでしっかり清掃し、乾いた布で水分や汚れを拭き取ります。その後、潤滑スプレーを適量(少なすぎず多すぎず)吹きかけます。スプレー後は窓を数回開閉させて、潤滑剤を均一に広げましょう。
戸車交換の安全ポイント
調整や潤滑でも改善しない場合は、戸車の交換が必要かもしれません。以下は、戸車交換を安全に行うためのポイントです。
- 適合する戸車の確認:
- サッシのメーカーや型番に合った戸車を選ぶ
- 迷った場合は古い戸車を持参して店舗で相談
- 準備と安全確保:
- 窓を全開にして固定(風で動かないように)
- 作業スペースの確保と養生
- 転倒防止のための足場の安定確認
- 交換手順:
- 戸車カバー(ある場合)を外す
- 固定ネジを外し、古い戸車を取り外す
- 戸車の溝を清掃する
- 新しい戸車を取り付け、固定ネジで固定
- カバーを元に戻す
- 交換後の調整:
- 戸車の高さ調整を行う
- 窓の開閉テストを行う
- 必要に応じて再調整
引用元:YKK AP 戸車メンテナンスガイド(2023年5月)
プロに依頼する判断基準と費用は?
DIYで対応できない場合や、より根本的な解決を望む場合は、専門業者への依頼を検討しましょう。ここでは、プロに依頼すべきケースと、その際の費用相場を解説します。
ガラス交換が必要なケースの目安
窓の隙間風問題の中には、ガラス自体を交換することで解決できるケースがあります。以下のような症状がある場合は、ガラス交換を検討する価値があります。
- ペアガラスの曇り:
- 二重ガラスの間に曇りや水滴が見られる
- 空気層の乾燥剤が飽和状態になっている
- ガラスとサッシの間の隙間:
- ガラス押さえゴムの劣化や脱落
- ガラスが固定枠内でずれている
- 古いシングルガラス:
- 断熱性能が低い(冬は冷たく、夏は暑い)
- 結露が著しい
- ガラスの損傷:
- ひび割れや欠け
- 衝撃による歪み
ガラス交換の費用相場は、サイズや種類によって大きく異なります。一般的な目安としては、以下のようになります。
- シングルガラス → シングルガラス:5,000~15,000円/㎡
- シングルガラス → ペアガラス(断熱タイプ):15,000~30,000円/㎡
- ペアガラス → ペアガラス:20,000~40,000円/㎡
- ペアガラス → トリプルガラス:30,000~60,000円/㎡
これに工賃(5,000~10,000円程度)が加算されます。なお、ガラス交換により断熱性能が大幅に向上することで、長期的には冷暖房費の節約につながるため、初期投資以上の効果が期待できる場合があります。
フレーム歪みのリスクと修復方法
アルミサッシのフレームに歪みがある場合、隙間風だけでなく、窓の開閉不良や雨漏りなど様々な問題が生じることがあります。以下のようなケースでは、フレームの修復が必要です。
- 歪みの症状:
- 窓が閉まりきらない
- 窓の上下や左右で隙間の大きさが明らかに異なる
- 窓を閉めると一部が強く当たり、一部が浮く
- ロックがかかりにくくなった
- 原因:
- 建物自体の沈下や歪み
- 窓の不適切な使用(強い力での開閉など)
- 経年変化による素材の劣化
- 地震や強風による影響
フレームの歪み修復は、高度な技術と専門工具が必要なため、DIYでの対応は困難です。専門業者に依頼することで、以下のような修復が可能です。
- 軽度の歪み:
- フレームの再調整(30,000~50,000円程度)
- 戸車や丁番の交換と調整(5,000~15,000円程度)
- 中度~重度の歪み:
- フレームの一部交換(50,000~100,000円程度)
- 窓全体の交換(80,000~200,000円程度)
- 最新の断熱サッシへのリフォーム(100,000~300,000円程度)
特に築20年以上の住宅で歪みが生じている場合は、部分的な修復よりも窓全体の交換を検討することで、気密性と断熱性を大幅に向上させることができます。現在の住宅用サッシは、20年前のものと比較して性能が格段に向上しています。
信頼できる業者を選ぶチェックポイント
窓の修理やリフォームを依頼する際は、信頼できる業者選びが重要です。トラブルを避けるためのチェックポイントを紹介します。
- 見積りの透明性:
- 材料費と工賃が明確に分かれている
- 追加費用の可能性がある場合、その条件が明記されている
- 見積書が詳細で分かりやすい
- 実績と評判:
- 施工事例の写真が豊富
- Google口コミなどの評価が高い
- SNSや公式サイトでの情報発信が活発
- 保証内容:
- 施工後の保証期間が明示されている(1年以上が望ましい)
- アフターサポートの内容が具体的
- メーカー保証と施工保証の違いが説明されている
- 対応の丁寧さ:
- 現地調査が丁寧
- 質問に対する回答が具体的で分かりやすい
- 強引な営業や即決を迫る姿勢がない
- 資格と保険:
- 建設業許可または関連資格を保有
- 工事保険に加入している
- 住宅リフォーム事業者団体登録制度への登録
複数の業者から見積りを取ることで、適正価格や一般的な工法を比較検討できます。また、アルミサッシの主要メーカー(LIXIL、YKK AP、三協アルミなど)の正規施工店である場合、専門知識と純正部品の調達ルートを持っているため安心です。
引用元:国民生活センター 住まいの修理トラブル事例(2024年1月更新)
季節ごとのメンテナンススケジュールは?
アルミサッシの問題を未然に防ぎ、長持ちさせるためには、季節ごとの適切なメンテナンスが効果的です。以下に、四季それぞれのメンテナンスポイントを解説します。
春:花粉対策と掃除で気密UP
春は窓を開ける機会が増える季節ですが、花粉や黄砂も気になる時期です。この時期に適したメンテナンス方法を紹介します。
- レールの清掃:
- 冬の間に溜まったホコリや汚れを除去
- 歯ブラシや綿棒を使って溝の奥まで丁寧に掃除
- 掃除機の細ノズルを使うと効率的
- 花粉対策:
- 窓の開閉部分に静電気防止スプレーを噴霧
- 花粉が付着しにくくなり、拭き取りも容易に
- パッキンのチェックと手入れ:
- 冬の寒さでひび割れが生じていないか確認
- シリコンスプレーを軽く吹きかけて保護
- 雨漏りチェック:
- 春の雨で雨漏りしないか確認
- シーリング(コーキング)の劣化をチェック
春のメンテナンスを怠ると、梅雨時期の雨漏りや、夏の虫の侵入につながる可能性があります。特に、レールに溜まった汚れは窓の開閉不良を引き起こし、長期的にはパッキンの摩耗を早める原因となります。
夏:紫外線ダメージを防ぐ簡単ケア
夏は強い日差しによる紫外線ダメージが懸念される季節です。アルミサッシのパーツを保護するためのケア方法を紹介します。
- 紫外線対策:
- パッキンや樹脂部品への紫外線保護スプレーの塗布
- 特に南向きや西向きの窓は劣化が早いので重点的に
- 結露対策:
- エアコン使用時の結露をこまめに拭き取る
- 結露防止スプレーの活用
- 虫対策:
- 戸車やレールの溝に虫が巣を作っていないか確認
- 特に蜂やアリの巣には注意
- 開閉チェック:
- 熱による膨張で開閉具合が変化していないか確認
- 必要に応じて戸車の調整
夏場はパッキンの劣化が最も進む時期です。紫外線と高温による影響を最小限に抑えるため、遮熱カーテンやブラインドの活用も効果的です。また、外出時には窓を少し開けたままにしないよう注意しましょう。スコールのような急な雨で雨水が侵入する恐れがあります。
秋:冷気前のすき間チェック
秋は冬の寒さに備えて、窓の隙間を重点的にチェックし、対策を講じる最適な時期です。
- 隙間風チェック:
- 前述の「紙テスト」などで窓全体の隙間をチェック
- 特に経年劣化が進むと秋から冬にかけて問題が顕在化
- 隙間テープの貼り替え:
- 前年に貼ったテープの劣化状況を確認
- 剥がれかけている場合は新しいものに交換
- 戸車の調整と注油:
- 夏の使用で摩耗した戸車を調整
- スムーズな開閉は気密性向上にも寄与
- 止水ラインのチェック:
- 窓の下部にある水抜き穴の掃除
- 排水がスムーズにできるよう異物を除去
特に9月~10月頃は、台風シーズンでもあります。強風で窓が揺れても気密性が保たれるよう、クレセント錠(窓ロック)の点検と調整も忘れずに行いましょう。錠が緩んでいると、風による振動で窓自体が損傷するリスクがあります。
冬:断熱アイテムで光熱費ダウン
冬は最も隙間風を感じる季節です。すでに対策済みの窓でも、追加の断熱対策で光熱費削減効果を高めることができます。
- 断熱シートの活用:
- 窓全体に貼る断熱シート(1,000~2,000円程度)
- 空気の層を作ることで断熱効果が向上
- 透明タイプなら採光を妨げない
- 断熱カーテンの設置:
- 厚手の生地や断熱裏地付きカーテン
- 窓枠よりも大きめサイズを選ぶと効果的
- すき間風の定期チェック:
- 外気温が特に下がる日に再度チェック
- 温度差で感じやすくなった隙間に追加対策
- 雪対策:
- 積雪地域では雪の重みによる窓の歪みに注意
- 窓の外側に雪が積もった場合は適宜除雪
冬場は室内の湿度管理も重要です。極端に乾燥した状態が続くと、木製サッシや複合サッシの場合は収縮して隙間が生じることがあります。適切な湿度(40~60%程度)を保つように心がけましょう。加湿器の使用や室内干しも効果的です。
まとめ
アルミサッシからの隙間風は、適切な診断と対策によって大幅に改善できる問題です。本記事で解説した内容をまとめると、以下のようになります。
- 隙間風の原因:
- フレームの経年変化による歪み
- パッキンの劣化
- 戸車やレールの不具合
- 自己診断方法:
- 紙テストで隙間を特定
- スマホアプリで温度差を可視化
- 気流計による正確な測定
- DIYで可能な対策:
- 隙間テープの適切な選択と貼り付け
- パッキンの交換
- 戸車の調整と潤滑
- プロに依頼すべきケース:
- ガラス自体の問題
- フレームの著しい歪み
- 複数の問題が重なっている場合
- 季節ごとのメンテナンス:
- 春:掃除と花粉対策
- 夏:紫外線からの保護
- 秋:冬に備えた隙間チェック
- 冬:追加の断熱対策
窓の気密性を高めることは、単に寒さを防ぐだけでなく、冷暖房効率の向上による光熱費の削減、結露防止による住宅の耐久性向上、さらには外部騒音の低減など、多くのメリットがあります。
特に隙間テープやパッキン交換などの基本的な対策は、数千円程度の費用で大きな効果が期待できます。一方で、窓全体の性能に問題がある場合は、長期的な視点で断熱性能の高いサッシへの交換も検討する価値があるでしょう。
まずは本記事で紹介した診断方法で、ご自宅の窓の状態を確認してみてください。そして、問題の程度に応じた対策を講じることで、快適で省エネな住環境を実現しましょう。
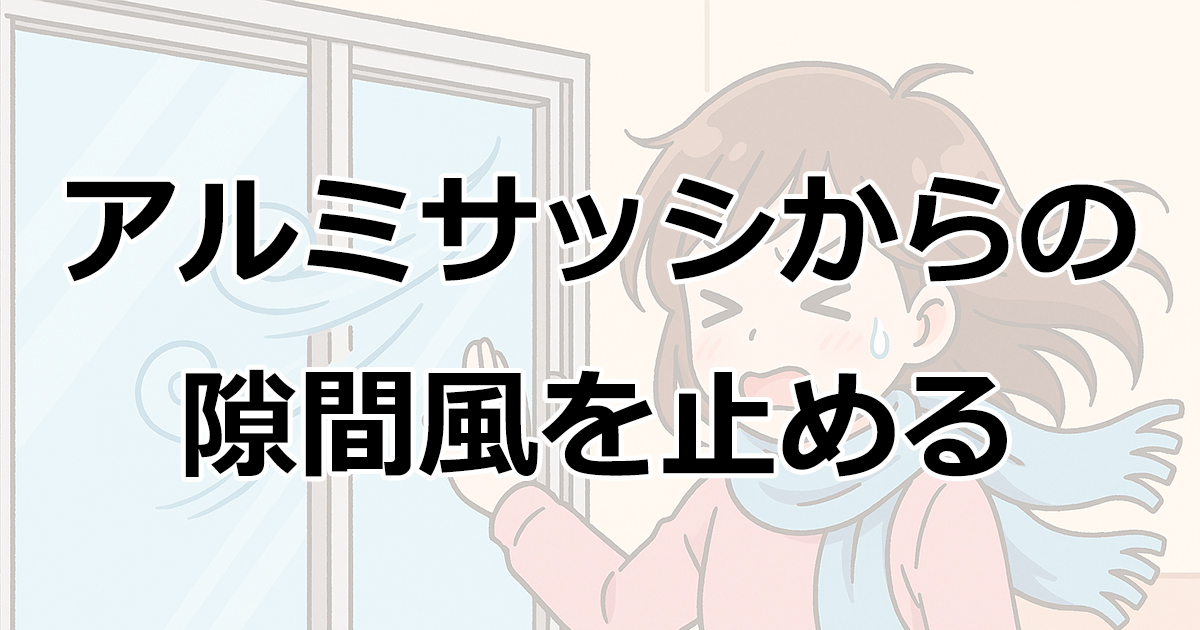
コメント